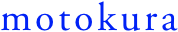2017年10月半ばに会社を辞め、世界一周の旅に出た写真家・ライターの佐田真人さん。旅先で尋ねられるたびに意識していた「日本人」であること。そんな佐田さんが、カンボジアでの家族との出会いによって変化したこととは?
すっかり馴染んだトゥクトゥクの背中に揺られ、ドライバーのコーさんの自宅へ向かう。歯を鳴らしながら彼の背中をのぞく。
「よくポロシャツ一枚で乗っていられるね!」なんていうと、こっちを振り返りながらグッドポーズをするコーさん。
彼の家族の話を聞いたときのこと。「マサトを子どもたちに会わせたい」という一言から、陽気な彼の自宅にお邪魔させてもらうことになった。
初めて足を踏み入れた8畳そこらの空間は、まるであの頃つくった秘密基地のように、いろんなものが所狭しとひしめき合っていた。
歯切れの良いハサミのリズムが耳に響く。
「妻は美容師なんだ」と今まさに仕事中の彼女と、3歳になる息子を紹介してくれた。手のひらを合わせ挨拶すると、そのすぐ後ろに腰を下ろし、夕飯の支度を始めた。
しばらくすると、コーさんのお兄さんにそのお嫁さん、小学生の長男長女が帰ってきた。
ご飯や鶏を丸ごと煮たもの、茹でた緑のやさいなど、食卓が整ったところで、「乾杯」の音頭とともに夕飯をいただく。
カタコト英語での会話だったけれど、互いの写真を見せ合いながら話していると、いつの間にか笑い打ち解けあっていた。
「こうして日本人とお酒を飲むのは初めてなんだ」というコーさんたち。
確かに仕事で日本人と話すことはあっても、自宅に招いてゆっくり話すことはあんまりないよなあ。そんなことを思いながら、「日本人」であることの自覚を取り戻しつつあった。
海外に行くと必ず尋ねられる「あなたがどこの人間であるか」。それに答えていると、否が応でも自分が日本人であることを意識する。
でもみんなが楽しそうに食卓を囲んでいるのを見ると、もはや異国の人である彼らと自分との間に境界線を引く必要はないんじゃないかと感じた。
抱えている悩みも、楽しいと思うことも、大して彼らと変わらないのだ。日本人としてではなく、自分がどうありたいか。結局ここに行きつくのかもしれない。
もしそうだとするならば、分け隔てなく、目の前の人を尊び、優しい人間でありたい。観光だけじゃ見えてこなかった彼らの温もりに触れ、そんなことを思った。
久しぶりに大勢で食べるご飯が身体に染みる。早くも家が恋しくなったぼくの旅は、まだまだ始まったばかりだ。