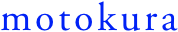歳を重ね、老人ホームに入ることになったなら。
そこからどうやって生きていくか、想像したことはありますか?
老人ホームでは、スタッフに助けてもらいながら、できるだけ生活に不自由することなく最期を迎える。筆者にとって老人ホームとは、そういう場所だと思っていました。
けれども宮崎県小林市の社会福祉法人・ときわ会を取材してから、「歳を重ねて老人ホームに入っても、生きている心地だけは忘れたくない」と思うように。


ときわ会は、高齢者福祉施設をはじめとし、温泉施設や児童・障がい福祉施設を運営する、小林市の社会福祉法人です。
副理事長を務めるのは、坂口和也さん。


坂口 和也(さかぐち かずや)
宮崎県小林市で生まれ育つ。祖父が坂口建設を立ち上げ、自身も大学卒業後、建設業の道へ。大手ゼネコン勤務を経て、小林市へUターン。現在は、社会福祉法人・ときわ会の副理事長と地域医療を考える会の会長を務める。
小林市の市民団体・地域医療を考える会の会長もされる坂口さんは、施設の利用者だけでなく、医療・介護現場で働く職員、地域住民にとって「歳を重ねても安心して暮らせる場づくり」に励んでいます。
そんな坂口さんに、もとくら編集部は今回、ときわ会の運営する広大な社会福祉施設をひとつ一つ案内してもらいました。

社会との繋がりを感じながら、生き生きと暮らす。
それは決して高齢者だけでなく、私たちにとってもとても大切なことのように思います。
そのヒントが、ときわ会の営みと、坂口さんの考える地域の医療福祉のあり方のお話から見えてきました。
部屋の外は、刺激に溢れている
ときわ会が設立されたのは、昭和49年。
今から43年前に、坂口さんのお父さまである坂口四郎さんが地域の方とともに立ち上げました。

施設が多数展開するこの一帯は、もともと山林や農地。それを四郎さんの寄付や地域住民の皆さんのご協力により、ときわ会の土地は徐々に拡大していったのだそう。
「これらの施設は、地域の方々の協力があって成り立っているんです」。坂口さんはこのように話します。

社会福祉法人ときわ会が経営するのは、高齢者福祉事業、児童福祉・児童障がい事業、温泉施設と多岐に渡ります。
介護レベルが高い方から、介護が必要のない方まで。本当にたくさんの地域住民が、この一帯の施設を利用しています。
たとえば、温泉施設「美人の湯」は一般開放されており、温泉だけでなく食事処としても利用されています。

マザーヒルズ保育園にはときわ会の職員や近隣医療機関等の職員の子どもたちが通い、老人ホームを利用する高齢者の方々との交流もあるのだそう。

それから、果樹園や温室ハウス、グラウンドゴルフ場があるのも、ときわ会の施設ならでは。

ときわ会の利用者のほとんどは、小林市をはじめとした宮崎県内のご高齢の方々になります。
ですのでやはり、高齢者向けの老人ホームや支援が充実しているのですが、一方でここまで紹介してきたように、提供するサービスが一般的に考えられる社会福祉の枠(介護や在宅支援)に留まらないことは驚きです。
一歩部屋から出れば、ワクワクすることがたくさん溢れている。この施設一帯がまるでひとつの町のようにも感じられます。

老人ホームが「それまでの生活の延長線」になるように
老人ホームやデイサービスを利用する高齢者の方々も、ただ受動的にサービスを受けるだけではありません。
果樹園やゴルフ場へと自ら赴いたり、子どもたちをはじめとした地域住民と、施設内で行われるイベントを通じて積極的に関わっています。
高齢者の方々が主体的に何かをしたり、地域の住民と交流を持つ。それは坂口さん自身が強く望むことでもありました。
「以前は、職員が良かれと思ってどんどん生活に介入し、安全面から外に連れ出すことも控えていたんです。
すると高齢者の方も『本当はこうしたい』という本心があっても、『迷惑をかけるから言わないほうがいいか』と気持ちを押し殺してしまったりしていた。
それと、『もしも骨折したら』『転倒したら』という考えが先行して、僕たち職員自体もずっと守りにはいっていました」

けれどそうではなく、「自分でできることは、なるべく自力でしていただいたほうが、その方のためになるのでは」という考え方に、職員たちが徐々に変わっていきました。
そのきっかけとなったのは、この施設に子どもたちが入ってきたこと。
ときわ会は、2年前、小林秀峰高校の農業科の学生さんたちと、施設内の畑を使ってキャベツやスイカなど育てる取り組みを始めました。
すると、職員が声をかけても外に出たがらなかった高齢者の方々が、高校生の声掛けで少しづつ外に出るようになったのです。
「最初はひとり、次は3人、10人と外に出る高齢者の方が増えて。そうすると職員も、一緒に外に出てみようか、となってきました。大人でもなく、おなじ立場の人でもなく、高校生の力で高齢者が自ら外に出たいと思うように。
それと同時に、職員会議でも『自分たちが老人ホームに入ることになって、“外に出ないで”“座っていて”と指示ばかりされるのってどうなんだろう?』という話になって。
『老人ホームに入ったからもう与えられたものを、ではなく。やっぱり年を重ねても生きている心地を感じたいし、感じてもらいたい』そこに共感し合いました。
老人ホームの生活が、それまでの生活の延長線上にあるものだと感じてもらいたいんです」

老人ホームに入っていちばん変わってしまうのは、きっと、それまでの生活で当たり前のように見えていた人たちの姿が見えなくなってしまうこと。スーパーや公園に行けば見れた地元の人たちの姿が、一気に遮断されてしまうことではないでしょうか。
けれど、ときわ会の老人ホームには、高校生が訪れ、保育園児を見ることができ、毎年開催されるお祭りで地元の人たちと交流することができます。そうそう、ときわ会が毎年主催する「地域交流夏祭り」には、800人もの地元の方々が訪れるんです。
ときわ会の取り組みは、高齢者の方々が老人ホームに入っても社会との繋がりを感じれる取り組みでもある。筆者はそう思いました。
地域の医療福祉が、健全な状態で続いていくには
もともとは、建設業界で働かれていた坂口さん。そんな坂口さんは、ときわ会の副理事長だけでなく、小林市の市民団体「地域医療を考える会」の会長も勤めています。
地域医療を考える会は、「医療従事者の方々がやりがいを持って働くことができ、住民誰もが病気になっても安心して暮らすことのできる地域づくり」を目指し活動している団体です。
坂口さんが、地元の医療福祉に尽力する理由を伺いました。

「僕には子どもが4人いるのですけど、次女は生まれたときに、心疾患を持っていたんです。
それがわかったのが熊本の震災直後だった。小林の小児科の先生に紹介された県立宮崎病院で『すぐに手術しないといけない』と言われたのですが、震災の影響で福岡の専門病院に空きがなくて。
それで、県立宮崎病院につないでもらい、福岡の病院に空きが出るまでそこで状態のコントロールをしてもらったんです。今でも思います。もしもあのとき、地元に小児科の先生がいなかったら? もしも県立宮崎病院が機能していなかったら? どうなっていたんだろう、と。
やっぱりやれることは自分たちでやらないといけない、誰かがやってくれるわけじゃないから」
地域の医療福祉のために、自分たちにできることはなんだろう?
それは、医療従事者や行政だけでなく、地域住民も一緒になって考えなければいけないと坂口さんは言います。
「地域の医療福祉のいちばんの課題は、働き手担い手が持続可能じゃない環境にあること。
今、社会保障費がどんどん絞られていく中で、田舎は特に職員自体の確保が大変な時代です。なので一生懸命やればやるだけ、その人に負担がかかるシステムになってきていると感じます。
たとえば産婦人科では、いつ赤ん坊が生まれてもいいように、24時間365日誰かが働いています。それを小林市では常勤の先生ひとりと、ふたりの外部の先生などに連携して対応していただき、なんとか支えていただいています」

「医療や福祉の世界で働いている人たちは、基本的には誰かのために身を削ってでも何かしたい、そんな熱い想いがある方ばかりです。それなのに、やって当たり前と思われたり、人の生死に関わるだけに、なにかあったらバッシングを受けやすい。責任の重い仕事なだけに、この業界にはそういう側面があります。
でもこの医療や社会福祉施設を利用するのは、やっぱり住民なわけです。だからこそ、医療福祉の現場で働く人と住民がお互いのことを理解しあって、住民が応援し、互いに支えあえるような関係になることが理想ではないかと思っています。
地域の医療福祉の状況を理解することによって、住民の検診率が上がって疾病予防が進んだり、かかりつけ医を持ったりするようになる。また、住民から理解を得ることで、ドクターはじめ医療福祉の現場のみなさんの負担も減ります」
医療福祉現場で働く方々と住民との相互理解のため、地域医療を考える会では、両者からのヒアリングや情報共有・相互理解に力を入れています。そのほか、現場のドクターや研修医や医学生の方々と住民の方々の勉強会や歓迎会を開催したり、市外のシンポジウムに出て小林市の医療福祉がよりよくなるための情報を仕入れたり。
今、特に注力しているのは、地元からドクターを育てることだと、坂口さんは教えてくれました。
欲しい未来を自分たちでつくる
坂口さんが目指すのは、「自分たちが年を重ねたとき、安心して暮らせる場所をつくる」こと。
それは、ときわ会の職員の方々にも日頃から伝え続けているのだそう。
「僕たちは僕たちの道を行って、入居者の人たちに安心して暮らしてもらいたい。
職員の皆さんにもよく聞きます。『自分たちが年を重ねたとき、今のままで、安心して老後を迎えられますか?』と。そうじゃなければ、やっぱりそれは今、僕たちが動かないと。
明日、すぐに変えられることではないので。今から僕らが少しずつ形にしていくことが大事だと思っています」

「わたしたちの業界は、決して老い先長くない方々と向き合うわけで。どんなにより良いケアを提供しても老いには抗えないところがあります。
でもそれだけじゃなくて、『今日は外に出てあんなことしましたね』『子どもが来たね』と話をして、あははって笑い声が聞こえると、職員がまず元気になる。職員が元気になるとやっぱり、『利用したい』『続けたい』『働いてみたい』と思ってくれる利用者も職員も増えます」
自分たちでできることをやっていくと、なんとなく明るくなっていく。
坂口さんは取材の最後、こんな言葉を残しました。
年を重ね、老人ホームに入る。そのときまでまだ時間がある筆者は、一体何ができるだろう? そんなことを考えさせられる取材でした。

(この記事は、宮崎県小林市と協働で製作する記事広告コンテンツです)
文/早川大輝
編集/小山内彩希
写真/土田凌