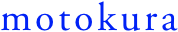宮崎県小林市の須木という地域には、山の中に小さなお菓子屋があります。
細道の入り口にかけられた看板を目印に、編集部が辿り着いたのが『洋菓子工房プチ・パリ』。

お菓子屋、というよりはまるで実家に帰ってきたかのような感覚になる外観。それもそのはず、プチ・パリは店長である前原宏美さんの実家の一部屋で開かれるお菓子屋なのです。
そのせいか、店内に入るとどこか懐かしい空気が漂っているように感じます。
プチ・パリが取り扱うのは、須木の栗や柚子など、地元の食材をふんだんに使用したお菓子の数々です。実際にお菓子を食べたもとくら編集部は、口々にその美味しさを語り、それぞれお土産を購入したほどのハマりようでした。
そんなプチ・パリのこだわりは、「買ってでも食べたいと思うお菓子をつくる」こと。

プチ・パリが魅力的に感じたのには、前原さんのおもてなし精神も関係していたようにも思います。
取材中、前原さんのお話からは、お店に来てくれるお客様、地域の人々、そして二人三脚で仕事をしているお父様への深い感謝を感じました。
つくりたいお菓子は「自分がお金を出してでも食べたいもの」


── 正直な第一印象を言うと、お菓子屋には見えない店内だなと思いました。ビールのポスターが貼ってあったり、お酒に合いそうなおつまみが並んでいたりで。
前原宏美(以下、前原) お酒が好きなので、お酒に合うお菓子もたくさん作っているんです。シュトーレンとかも作っていますが、ワインや焼酎などをたくさん入れていて。特に、九州をはじめ、日本中でも人気を博している須木酒造さんの焼酎は、とてもフルーティーで、お菓子ともよく合います。
お菓子屋さんとしては、あまり普通ではないかもしれませんね。甘いお菓子だけを作るのではなく、辛いお菓子も作ってしまおうとするのがプチ・パリです。
── 商品を考えるときの基準はありますか?
前原 自分が買ってでも食べたいものかどうか、です。そうじゃないと作っていて楽しくないじゃないですか。手作りだからどうしても、注文が来たら忙しくなってしまうのに、楽しくなかったら作るのが嫌になっちゃうので。
だから、私が食べたいものを作っています。例えば、甘いものを食べているときって、反対にしょっぱいものや辛いものが食べたくなりますよね。辛いものを食べたいから、じゃあ作っちゃおうという感じで。
── 自分が食べたいものを作ると言っても、商品として出すからにはそこに迷いなどが生じませんか?
前原 自分が食べたいか、買ってでも食べたいかは商品を出すときの基準ですが、自分の意見だけでお菓子を作らないようにしています。ちゃんと売れるものにして世に出していきたいから。
なので、迷いは常にありますね。よく友だちに「こんな新作どうですか?」と意見を求めるようにしています。思ったことをズバッと言ってくれる、信頼できる友だちが周りに多いんです。
── プチ・パリの人気商品を教えてください。
前原 よく口コミなどで取り上げられるのは、「栗トリュフ」ですね。もちろん、自分が食べたいから作り始めて、「美味しそう、これならお金を出してでも食べたい」となってから商品として提供を始めました。

前原 これ最初は、焼き栗を栗きんとんで包んでいたんです。でもそれだと面白みに欠けるじゃないですか。
「自分はどうしたら買いたいと思うかな?」って考えたときに、チョコをかけることを思いついたんです。栗だけでは食べてて飽きるかもしれないけど、チョコがかかっていたらふたつの味になるので、飽きないなと。
「栗トリュフ」ともうひとつ、クリスマスの予約限定で出している「くりのままで」も人気ですね。


前原 これも初め、一番下のケーキは普通のスポンジケーキだったんですけど、周りの人の意見を聞いて、チーズケーキにしてみたら美味しくて。買ってでも食べたい商品になりました。
「栗トリュフ」も「くりのままで」も、基本的に須木地域で採れる栗を使用しています。この辺は栗がたくさん採れるのに、ちょっと傷がついてたり形が悪かったりといった理由で捨ててしまう農家さんが、結構多いんです。
うちではそういった市場に出回らないものを譲ってもらい、活用しています。
実演販売の手伝いとともに育っていった夢
── そもそも自分のお店を持ちたいと思ったきっかけは、何だったんですか?
前原 高校生の頃から、父の会社を手伝っていたんです。父は、九州を拠点に日本各地でたこ焼きやクレープの実演販売をしていて、私もそこに付いて行っていました。
おもに佐賀や長崎の百貨店で、お客さんを相手に実演販売をしていたのですが、そんな経験、なかなか出来ないじゃないですか。初めは漠然と「こんな世界もあるんだなぁ、面白いなぁ」という憧れだったのが、実演販売を経験するうちに、「自分のお店を持ってみたい」と、具体化していきました。
── 「お店を持ちたい」と意識し始めてからは、何をはじめましたか?
前原 商業高校に通いながら、お店を開業することを見据えて事務系の資格を取りました。そのあと1年間は、バイトでお金を貯め、調理師免許を取るために福岡の調理師専門学校に行きました。
免許取得後は地元の会社で働いていたのですが、結婚や妊娠を機に退職したんです。ちょうどその頃ですね。父から「家の裏の車庫を工場にしたい」と話をされて。「一緒にお店をやろう」ということになり、父の会社に入ったんです。
── プチ・パリは、形としてはお父様の会社・河野フーズの洋菓子部門なんですよね。
前原 そうなんです。父は実演販売がメインなのでお店にはいませんけど、今でも小林市の大型スーパー「まちなか松栄」などで実演販売をしています。

── 実演販売を面白いと感じていたのなら、「お店を持つ」ではなく、移動しながら実演販売をしていくという選択肢もあったのではと思ったのですが、それは考えなかったんですか?
前原 父の仕事を母も手伝っていたのですが、遠方での実演販売で、両親が1週間くらい家を空けることが珍しくなかったんです。でも私は、家庭を持ったことで、そういう生活はしたくないなって。子どもと一緒にいる時間を減らしてまでやりたい仕事かって言うと、そうではないなと思いました。
もちろん、私の生活に合わなかっただけで、実演販売は良いところもたくさんあります。新作のお菓子を試しに作ってみたときとか、お客さんの率直な意見を直接聞ける場を持っているということですからね。そこで得た意見をもとに、商品を改良していけるのは、うちの強みかなと。
私もたまに実演販売に出るんですけど、「あんたもよか(いい)大人になったね」ってお客さんから言われるんです。そういう声をかけてくれるのは、高校生の頃から私のことを知ってくれているお客さん。私も「よか大人になりました」って返して。こういうのはなんか良いなぁって思います。
── ああ、良いですね。
前原 普通のお菓子屋ではできないことですよね。父と二人三脚だからこそ、できているんだと思います。この歳になっても、たまに喧嘩してしまうんですけどね(笑)。
地域の人たちとの、持ちつ持たれつの関係
── お父様から影響を受けている部分はありますか?
前原 父は小林出身なんですけど、地域との関わりの強さを感じます。たとえばうちは栗を使った商品が多いじゃないですか。そうすると、地域の方が「あんたんとこも使うやろ。あそこにも植えているから拾っていいよ」って言ってくれるんです。
それは父のネットワークなんですよ。父はたこ焼きを地域の方に振る舞ったりしていて、その繋がりでいろんな情報を持ってきます。おもしろいですよね。
── もとくら編集部も地域取材を続ける中で、地域のネットワークの重要性を感じます。地域と心地いい関係を続けていく秘訣って何でしょうか。
前原 お互い様、みたいな意識を持つことじゃないですかね。田舎では「してもらったら返す」というのが基本。助けてもらったら、次は別の形で返すんです。
たとえば、年配の人がパソコンで困っているとき、私が手伝うことがあるんですけど。そうすると今度は私が漬物の作り方で困っていると助けてくれる。そういった、持ちつ持たれつを大切にすることで、心地いい関係が続いている気がします。
── それぞれが、自分の得意なもので支え合っている、と。プチ・パリの店内に、小林で働く他の方々の商品が置いてあるのも、そこに繋がる話なのかなと思いました。


前原 結構、遠方から来るお客さんが多くて。
「小林には何を目当てに来たんですか?」って聞くと、「うちを目指してきた」って言うんです。わざわざ、こんな山の中まで来ていただいたのに、おもてなしができないのは心苦しくて。だから少しでも、小林の他の良いお店のモノが一緒に見られたらいいなと、置いてるんです。
本当は、もう少しゆとりある空間を作りたいんですけどね。それは、次の目標として頑張ろうと思っています。
── 具体的に考えていることってあるんですか?
前原 遠方から来てくれたお客さんに、おもてなしができるような古民家カフェを作れたらいいなと思っています。何年後になるのかはわからないですけど。
もしできたら、楽しそうだと思うんです。このあたりには、結構空き家もあるので、少しずつ、少しずつでも進めていければなと。夢を大きく持っています。
(この記事は、宮崎県小林市と協働で製作する記事広告コンテンツです)
文/早川大輝
編集/小山内彩希
写真/土田凌