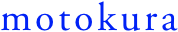佐賀県・嬉野市で季節ごとに年4回開催されている、「嬉野茶」「肥前吉田焼」「温泉」が融合したイベント・「嬉野茶時(うれしのちゃどき)」。
東京や北海道から足を運ぶ人が絶えないイベントができるまでの歴史や想いを、発起人の3人に伺いました。
(聞き手:最所あさみ)
淘汰されゆく旅館、荒地になっていく茶畑……。温泉地としての嬉野のこれまで

古くから「日本三大美肌の湯」とも言われ、温泉地として栄えてきた佐賀・嬉野。
全盛期は大小80軒以上あった旅館が、団体旅行の減少やニーズの変化の中で淘汰され、現在では大小30軒程まで減少。
インバウンド需要のおかげで一時元気を取り戻しましたが、やはり国内需要は減り続け、生き残っている旅館も決して安泰ではなく、どこも青色吐息の状況は変わりません。

また、嬉野の特産物であるお茶も、ほかの地方と同じく後継者不足に悩んでいます。
昔は一面茶畑だった敷地の中に、手入れされず伸び放題になってしまった区画も、ぽつりぽつりと現れるようになってきました。
「これから、嬉野という地をどうしていくか」
それぞれのやり方でこの問題に取り組んでいた3人が出会ったのは、必然だったのかもしれません。

偶然が重なると、それはやがて道になる


「嬉野茶時」の舞台は、嬉野を代表する老舗旅館・和多屋(わたや)別荘。
昭和天皇も宿泊されたことがある由緒正しい旅館ですが、代表の小原さんが3代目として引き継いだ時は多額の負債を抱え、経営再建の真っ只中でした。
「まずはお取引先にきちんと未払金をお支払いすることで精一杯。『地域のために』とか『地元の人たちとの関係構築をなど』とかって、まったく考えられなかったんですよね。
再建中は敷地からほとんど外に出ることもなく、ただひたすら再建に向けて仕事に邁進していました」(小原さん)

その徹底した努力の結果、2年で未払金を清算することができ、これから和多屋としてどうしていくかを考えていたときに出会ったのが、大村屋の15代目を務める北川さんでした。
「小原さんのお名前は組合の集まりで耳にしたことはあったのですが、再建中はそうした集まりにも一切顔を出されなかったので、ほとんどお会いしたことがなくて(笑)。
でも、ある日共通の知り合いに引き合わせていただく機会があって、そこから意気投合しました」(北川さん)
北川さんは、25歳で実家に戻り15代目として老舗旅館・大村屋の代表となった人物。
引き継ぎ当初から若い感性でユニークなイベントやフェアを開催してきたものの、自分たちだけではまち全体を盛り上げることにはつながらないという課題を感じていました。
「そんなときに、行政側から『有田焼創業400年の節目の年に、同じやきもの文化圏の嬉野でも、まちを盛り上げたい』という企画案をもらったんです」(小原さん)

嬉野市から持ち込まれたプランに対して、「もっと嬉野の魅力を伝えるやり方があるはず」と小原さんが企画書を作り、行政側を説得したのが2016年5月。
5月といえば新茶の季節であり、茶農家さんたちが1年で一番忙しい時期です。収穫と出荷で慌ただしい1日を過ごしていた副島さんのもとに、実行委員の方が企画書を持参したのはそんな繁忙期のことでした。
「外資系ホテルのイメージカットがふんだんに盛り込まれた企画書をはじめて見たとき、正直、どんなイベントになるのかまったく想像ができなかった」、と笑うのは茶農園の副島さんです。

「私は嬉野生まれ嬉野育ちですから、東京にあるような外資系ホテルの名前を言われてもまったくピンとこなかったんですよね(笑)。
最初は企画書を見ても本当に成功するのか半信半疑でした。でも、嬉野の茶農家を変えるきっかけになるかもしれないと思い、新しいことにチャレンジしている茶農家さんたちにも声をかけてみたんです」(副島さん)
そこからたった3ヶ月──。
2016年8月、はじめての「嬉野茶時」が開催されることになります。
身を委ねられる歴史があるからこそ、ゆるがないもの


はじめは1回限りのイベントで終わるものとしてはじまった「嬉野茶時」。にも関わらず、初回の準備期間中にはすでに「次をやろう」という流れに自然となっていたのだそうです。
初回の「うれしの晩夏」が終わると、3ヶ月後に「うれしの深秋」、「うれしの春夢」と四季にあわせたシリーズ展開を開始。
たった1年で、毎回足を運んでくれるお客様も現れました。

「嬉野茶時」が1回限りの打ち上げ花火になってしまわず、自然と続く文化になっていったのはなぜなのか。
その理由を、3人は少しずつ表現を変えながら、言葉にしてくださいました。

「私たち大村屋でも様々なイベントを企画してきましたが、嬉野茶時の場合は嬉野という土地の歴史に根ざしていたのが大きかったように思います。
長い時間をかけて醸成された嬉野の文化があるからこそ、そこに現代的なビジュアルイメージをのせることで、人を熱狂させるエネルギーが生まれたのではないかと思っています」(北川さん)
「茶農家は、味には自信があっても見せ方がわからない人たちが多いものです。小原さん・北川さんの力で新しい見せ方に出会い、自分たちの仕事が評価される嬉しさが、『またやろう』の原動力になっているように思います」(副島さん)
「身を委ねられる歴史がある、というのは私たちの強みだと思います。嬉野というまちの歴史は地層が深く、固い地盤の上に出来上がっています。だからこそ、その上に自由に新しいものを建てることができるのです」(小原さん)

3人の話に共通していたのは、その土地に積み上げられてきた歴史的な価値への強い自信です。
「嬉野らしさ」について語る時、ほかの地域と比較するようなフレーズが一切でてこなかったことからも、相対的な自信ではなく、自分たち自身を深く理解しているからこそのそれを感じました。
その土地らしさは、他者と比較して作り出すものではなく、積み重ねられてきた歴史の中にすでにある。
私たちが見つめるべきものは、よその成功事例よりも自分たち自身なのかもしれません。
そんな3人の話を反芻していたとき、小林秀雄のこんな言葉を思い出しました。
「君という人間は、この日本に生まれ、日本語を使っている人種なのだ。
それは君にとって、非常に大事なコンディションだろ?
そのコンディションを離れて、別の何かにすがっても立派なことはできないのだ」(「学生との対話」小林秀雄)
3人から感じたしなやかな強さは、自分たちの “コンディション”を深く理解し、それを受容していればこそなのだと気づいた瞬間でした。
「精神性を伝え、のこす」生産地と観光の新しい関係を、嬉野から

「これだけたくさんの人がプロジェクトに関わっていると、毎回企画をまとめるのが大変なのではないですか?」
そんな私(最所)の問いに、3人は顔を見合わせながら、「ほとんど議論になったことはないですね」と答えてくれました。
全員の方向性をあわせるため、嬉野茶時では参加前に読んでもらう文章があり、すべての決断はその文章に沿って決定されるのだそうです。そして、全員が共通して持っているのは「嬉野の精神性を伝え、のこすことが自分たちの仕事である」という意識です。

「時代にあわせて世に出すもののかたちは変わっても、嬉野というまちに受け継がれてきた精神性を表現する」。
それが嬉野茶時の目的なのだと、強い眼差しで語ってくださいました。
「私たちは、嬉野茶時をオープンソースだと思っています。関わってくれた全員が自分のビジネスにつながるように、嬉野茶時という取り組みを活用してほしい。
でも、そこに『平等』という意識を持ち込みたくはありません。そのためにクオリティが犠牲になってしまっては本末転倒だからです。だから、開催場所もメニューも、平等に持ち回りするのではなくそのときベストだと思うものを選んでいます」(小原さん)

コミュニティが濃ければ濃いほど「平等」への意識が強くなり、もともと誰に向けた取り組みだったかを忘れてしまうという現象を、しばしば目にすることがあります。
嬉野茶時が短期間で根強いファンを獲得できたのは、それぞれの強みを出し合いながらも、我田引水にならず「嬉野茶時」そのものを盛り上げようという共通認識のバランスがとれているからなのかもしれません。
「これから、どうしていきますか?」

インタビューの最後に「これから、嬉野茶時を通してどんなことを成し遂げたいですか?」と質問したところ、北川さんから「ブルゴーニュのようなまちを目指したい」という答えが返ってきました。
生産地と観光を有機的につなげ、嬉野が誇るお茶文化を日常レベルまで引き上げていきたいのだと。
ただ見た目が綺麗なだけではなく、そこに深い歴史と精神性が潜む嬉野茶時は、触れた人みんなの心を打つコンテンツとして今後ますます広がりを見せていきそうです。
 さらに、インタビュー後に私たちが足を向けたのは、嬉野の街を見下ろす茶畑の中にある「天茶台」。
さらに、インタビュー後に私たちが足を向けたのは、嬉野の街を見下ろす茶畑の中にある「天茶台」。
嬉野茶時のイベントで野点用に使用した台を、副島さんが所有する茶畑に移して出来上がった嬉野の新しいシンボルとも言える場所です。
緑がまぶしい茶畑に囲まれた空間で凛とした空気を吸い込むと、自分の中にある迷いや悩みがすうっと抜けていくような、そんな不思議な感覚が人の心を掴むのかもしれません。

東京で暮らしていると、「何のために働くのか」「自分とは何か」と、根無し草のような自分の価値を疑う瞬間を感じる人も少なくないと思います。
地方に暮らす人が眩しく見えるのは、そんな悩みを一切もつことなく、絶対的に信じる価値があるからなのかもしれません。

自分がもつ使命とは「この土地の精神性を伝え残していくこと」であると信じて疑わない3人のお話を伺う中で、私も「自分が伝え残したいものは何だろうか」と考えるようになりました。
そしてきっとその答えは、どこかに落ちているものではなく、すでに自分自身の中にあるはずなのです。
受け継いでいくべき「核」が時代を反映した「器」に出会ったとき、人の心を動かす大きなエネルギーに変わる。
茶畑の澄んだ静寂の中で、そう確信したインタビューでした。
 お話をうかがった方々
お話をうかがった方々
小原 嘉元(こはら よしもと)
「和多屋別荘」代表取締役。約10年の旅館再生コンサルティング業を経て、2013年より和多屋別荘の3代目として代表に就任。旅館内の装飾や内装ディレクションを自ら務め、そのセンスは類を見ない。自社の大工とともに365日、サグラダ・ファミリアのように改修を続けている。嬉野の歴史的文化価値の向上に日々奔走中。
■「和多屋別荘」公式サイト
北川 健太(きたがわ けんた)
嬉野でもっとも古い歴史を持つ老舗旅館「大村屋」15代目の代表取締役。毎月最終日曜日に開催している「宿泊者vs旅館 スリッパ温泉卓球大会」をはじめ、「もみフェス」「いとう写真館」など嬉野温泉でワクワクするイベントを多数仕掛ける。2016年より「湯上がりを音楽と本で楽しむ宿」として旅館の一部を大きくリニューアル。ビートルズマニアでもある。
■天保元年創業の旅館「大村屋」公式サイト
■Twitter(@oomuraya)
副島 仁(そえじま ひとし)
「副島園」4代目。静岡にある茶業試験場で学び、東京の茶問屋に就職。すぐに都会に馴染めないと痛感し、ほどなく故郷へ戻り22歳で就農。33歳のときに、自家栽培したお茶で全量小売を達成。同年、茶業界初の農業賞 最優秀賞(経営の部)を受賞。現在は作付け面積の半分を完全無農薬で栽培し、烏龍茶など新しいお茶作りに挑戦中。
■茶農家「副島園」公式サイト
- 「嬉野茶時」公式サイトはこちら
文/最所あさみ
撮影・編集/伊佐知美
(この記事は、佐賀県と協働で製作する記事広告コンテンツです)