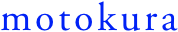今、心のよりどころとなるモノとは、一体どんなモノか。
はじめはこんなテーマで『わたしのよりどころ特集』のひと記事目を書こうとしていた。そのために、哲学者で民藝に造詣が深い鞍田崇先生にオンライン取材をご依頼したのだが、お話を伺っていくうちに、テーマは方向転換することに・・・。

鞍田 崇(くらた たかし)
哲学者、明治大学准教授。1970年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。総合地球環境学研究所(地球研)を経て、現職。研究テーマは、地球規模での環境・社会変化に対する人文的アプローチの検討。主な著書は、 『〈民藝〉のレッスン—つたなさの技法』など。
民藝運動の父・柳宗悦は、生活道具だった民藝品に‟用の美”という価値を見出し、「機能性」と「美しさ」を兼ね備えたものとした。鞍田先生がこの2つに加え、民藝に見出したのは「いとおしさ」。民藝を捉えなおしながらこれからの暮らしや社会を考える鞍田先生に「現代社会とモノと心」を軸にお話を伺おうとした。「今、どんな要素を兼ね備えたモノが、よりどころとしての役割を果たせるのか」のヒントを得ようとしたのだ。
だが、1年半ぶりに(画面越しだが)お会いする鞍田先生の、まだ近況程度しか聞いていない段階で、気づいてしまった。「あっ、このテーマはナンセンスだった!」と。何が心のよりどころとなるかは、あまり重要ではなかった。それどころか、「これがよりどころではないか」と解のようなものを提示すること自体に危うさがあると気づいたのだ。

「私たちが本当に心のよりどころとなるモノに出会うために模索していくべきは、きっとゴールではない。見つめなおすべきは、その道のり──プロセスについてだ」
取材の中でこのように思い直した筆者は、冒頭のテーマを以下のように改めた。
今、心のよりどころとなるモノを、どうやって見つけていくべきか。
最短距離で出会えないモノがおもしろかったりする
── 編集部は、鞍田先生と『福島県昭和村特集』でご一緒させていただき、中でも土から糸になる「からむし」を中心に、自然のサイクルと共に生きる暮らし方について考えてきました。研究の一環で全国でフィールドワークをされている鞍田先生ですが、最近(2021年4月)はどのようにお過ごしでしたか?
鞍田 仕事のことで言うと、やっぱり移動が制限されるこのご時世、地方にはなかなか行けなくなりました。メインフィールドである昭和村は、もともと高齢化率の高いエリアでもあるので、なおさら。
一方で、自宅周辺を歩くことは増えました。
僕、東京・三鷹に住んでいるんですけど、都心部に通勤通学する人たちのベッドタウンみたいなところで、個人商店とか、そんなにある感じではなかったんです。でもいつも歩く駅までの道を、ちょっと遠回りすると、おもしろいお店があったり、なんてことに気づいたんです。その発見を「豊かさ」なんて大上段に構えるつもりはないのですけど、それまで線でしかなかった街が面になっていくような感覚がありました。

── 新たな風景との出会いで、街が線から面になった。
鞍田 線の感覚だったときは、極端に言うと、自宅と駅の間をいかに素早く動くかだけを考えていたから、いつも限定された風景しか見ていない。雑味がない風景というか。
でも本当は、その設定されている目的以外の方に少しでも視点を移すと、線でしかなかったところにも、いろんな要素が潜んでいるはずなんですよね。
子どもの学校からの帰り道の歩き方に似ているかな。子どもはよく、同じ道を歩いていてもいちいち立ち止まったり、何かをのぞき込んでみたりして、ジグザグに歩くじゃないですか。そうやって街が面に見えていくうちに、すごく街の居心地が良くなったというのはあったかな。
── ゴールに最短距離で向かうばかりのつまらなさは、思い当たる節があります。例えば本屋でも「こういう人には、この本です」と親切すぎるポップなんかが置かれている時があるじゃないですか。
鞍田 めっちゃわかる(笑)。僕は基本、本はジャケ買い派なんです。「たまたま表紙の装丁だったり、タイトルの一文字だったりに惹かれて手に取ってみたら、なんかめっちゃおもしろかった」みたいなね。こういう出会い方は、ゴールが設定されたところにいかに効率よく行くかという発想からは、出てこない出会い方なんだよね。
たぶん、コロナ前の社会やビジネスモデルは、いかにゴールを早く提供するか、あるいは個人レベルでも、いかにゴールに早く着くかを研究していて。間違いではないけれどもそれ一辺倒になっていた節があったと思います。でも、ひとまず動けない、会えないという社会状況になり、そのスピード感も収まってきた。そこでやっともう一回僕らはゴールまでの別のアプローチを探すことができたはずなのに、去年1年間ステイホームを過ごす中で、「また体(てい)の良いゴールの提供が、社会から始まってしまっているなぁ」と釈然としなかった。
去年は特に、身近な生活とか時間の中に豊かさを見出していこうって動きが前面に出てきて、「家で過ごすときこういう良いモノもありますよ」といったステイホーム絡みのビジネスもどんどん出てきたけど。そのステイホームさえもお膳立てされようとしている風潮に、違和感を覚えていました。
なので僕自身は、なんかマニュアルに乗っかっているつもりはないけど、気が付くと乗せられてきたこれまでの自分たちの生き方や生活を、一回外す機会なんちゃうかな?って、今は思うんですよ。
新しい時代はプロセスを楽しめるか?
── 鞍田先生が考える、ゴールに最短距離で行くのとは別のアプローチとは?
鞍田 これまでが少しでも早くゴールに行こうとした時代だったなら、もう少しゆっくりとその間のプロセスを楽しむような過ごし方をしてもいいかもしれないよね。
ゆっくりさ加減をどの辺にチューニングするのかは人それぞれだと思いますけど。地方の時間軸に合わせる人もいれば、地球規模のサイクルに身を任せる人もいるかもしれない。これからは、社会のリズム感ではなく、自分のリズム感でゴールに近づいていく人が増えていくと思うんですよ。
── そういう気運を感じている?
鞍田 何か一つ、今までの社会から脱皮、脱却しようとする気運は感じます。これは受け売りになるんですけど、今年の1月に亡くなられた作家の半藤一利さん(享年90)の『昭和史』にとても興味深い話があります。その本の冒頭では、日本の近現代の盛衰は40年周期のサイクルで見ることができるということが書かれているんです。
1865年に日本は本格的に開国へと動き出していきますが、半藤さんはそれを日本の近代化の幕開けと位置づけている。そこから40年後の1905年は、日露戦争で日本が勝った年。つまりわずか40年で近代国家を作り上げたということです。ところが次の40年で起きたことは、1945年に第二次世界大戦での敗戦。40年で作り上げた国を40年かけてまた潰しちゃったんです。半藤さんはGHQの占領期を経てサンフランシスコ条約が発効された1952年あたりを国家建設のリスタートとしているけど、そこから40年後ってバブル。たしかに40年で国を作っては、また次の40年で滅ぼしてということを繰り返している。そして半藤さんは、再び40年をかけて国を滅ぼしているのが今なんじゃないか、というふうなことを言っているんです。
その周期に則って考えると、今がバブル崩壊から30年くらいになるでしょう。第二次世界大戦後のように国中が焦土になることはないにしても、そろそろ次のサイクルに入ろうとするタイミングなんかな、と『昭和史』を読んで思ったりしています。
物言わぬモノから自信や安心感を得る
── これまでの社会では、使うにしろ、作るにしろ、民藝も含めてあらゆるモノが人の心のよりどころになってきた側面があると思います。変わりゆく社会でも、モノは人の心のよりどころになるんでしょうか。
鞍田 僕の中では、モノは裏切らないっていうがある。人は裏切るし嘘もつくけど、モノは向き合えば向き合うほど、裏切らないというか。最近読んだ小説にも似たような話がありました。藤原新也さんの短編集『コスモスの影にはいつも誰かが隠れている』なんですけど、その中に収録されている『アジサイの頃』というお話で。
若い男性の写真家のお話なんです。彼がまだ売れなかった頃、お寺で季節の写真の物撮りなんかをやっていたんですけど、たまに変化を加えるために編集部がモデルを交えるような企画も持ってくる。けれど駆け出しの写真家という理由で冷たくあしらわれたりしてしまう。そんな中、彼がこんなふうに言うんです。「写真を撮られるということは大変なことなのに、何かポーズも姿勢も変にマニュアルっぽくて全然気持ちが入っていない、こんなものならモデルなんていなくても、花や寺だけと対面してる方がいいなといつも思っていました。静物は見つめれば見つめるほどその分だけこちらを見つめ返してくるような純粋なところがありますから」と。

── 最後の一文が、モノは嘘をつかないという鞍田先生のお話と重なりますね。モノが自分を見つめ返してくれる感覚について、もう少し聞きたいです。
鞍田 同じモノが万人の心に作用するわけじゃないし、一人の心に対してどんなモノでも同じように作用するわけでもない。つまり、僕と誰かのアンテナにビビッとくるものは当然違うし、さっきの本屋でジャケ買いの話だと、平積みの本がなんでもすべて僕の心にヒットするわけでもないということなんですけど。
だからこそ、「あ、こういうものに反応するわたし」ということに気づけるきっかけになる。モノは物言わないからこそ、自発的に気づかせてくれたりもします。
そうやって立ち止まったり迷ったりして発見したのは、どんなモノであってもいいということです。そういうモノを発見した私の中の「ある部分」にモノを通して気づけることが、「私はまだ大丈夫だ」って思える自信につながるというか。自分にとって必要で、自分が愛せるモノを見つけられる力が、まだ枯れていないって思える。それって結構、嬉しかったり、安心したりするんじゃないかと。
── 改めて、良い・悪いの基準が設定されたモノではなく、自分のプロセスでモノを選び取って愛着を感じていくために、どういったことを心がけていけばいいのでしょう?
鞍田 やっぱり、モノを見れば見るほど、人に会えば会うほど、何気ないものを見るときの解像度って上がっていくものです。そしてそれが、それまでの自分が特別じゃないふうに見ていたものも特別に思えることにつながってくる。
なので経験がすべてというわけではないけど、いろんな人に会い、いろんなものを見て、いろんな街に出かけということの積み重ねが、モノを見る解像度を上げていくんかなという気はしていて。そのときに理想的なのはやっぱりアナログな感じというか、肌感覚で空気感と共に味わうのが近道かなと思います。
まずは今まで歩いていた道を、今日はちょっと寄り道してみようと変えてみるだけでいい。駅と家の間のなんでもない、敷石の隙間から生える雑草の一つを見ても感動する自分って、ちゃんといたりすると思います。
取材のこぼれ話

鞍田先生はコロナ禍で料理をする機会が増えたそう。きっかけは、民藝関係で関わった人たちの営みが、このご時世で改めてたくましく感じたことだったと言う。「彼らがこういう状況でますますたくましくも見えるぐらいに自分の手を通してモノを生み出している一方で、何も作らない自分っていうもののひ弱さを痛感して……」。こんな意識から積極的に台所に立つようになり、今では「最近は本当に料理が楽しくて」と生き生きと話すほど。取材の中で「モノが自信を与える」という話があったが、鞍田先生のエピソードから、「作る」というのはそこによく応えた行為かもしれないと思ったりした。
文/小山内彩希