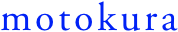人にはたくさんの一面があるように、人が使う「言葉」にもいろんな一面があります。この特集では、言葉の持つ「一面」を、日頃から言葉を観察する人たちと一緒に紐解いていきます。これからどのように言葉を使い、受け止めていくか。今と未来を生きる人たちの、参考になりますように。
誰かの心を揺さぶる言葉と、そうでない言葉。
ふたつを分けるのは、人の手のような「温度」が言葉にこもっているかどうか、なのかもしれない。

今年の冬。
筆者は『生きることから逃げないために、あの日僕らは逃げ出した(通称:生き逃げ)』という演劇作品を、新宿のライブハウスにて観劇した。
この『生き逃げ』という作品は、ライブハウスを拠点とし、演劇を繰り広げながら劇中では生バンドをバックにライブパフォーマンスを何曲も披露する。ありとあらゆる表現を全身で味わえる、新感覚のライブハウス演劇だ。
生き逃げは「囚人達の脱獄ストーリー」。
主人公の囚人たちは、大切な人が存在しない今に絶望していたり、何者にもなれない平凡な自分を呪っていたりなど、現代人にも通じる悩みや悲しみを抱えている。そんな彼らが、ありたい生き方を生き直すため脱獄を計画する、というのが物語の大きな軸となっている。
筆者は、第一回公演を観劇した後も、『第一回公演のアフタートークイベント』、劇中挿入歌を披露した横浜でのライブフェス、そして第二回公演『生きることから逃げないために、あの日僕らは逃げ出した〜逆襲の花束〜』までこの作品を追いかけた。
ひとつ。生き逃げに惹かれ続ける理由に、生き逃げに登場する「叫び」がある。
生き逃げには、囚人たちが脚本をビリビリに破き「心のうちを叫ぶ」シーンがあるのだけど。その叫んでいる言葉が、何度この作品を観に行っても新鮮で、いつもまっすぐ自分の元に届くのだ。
それは彼らの言葉が絶対的に素敵なのか、それとももっと何か別の、心に届く要素があるのか。

「『生き逃げ』という作品の言葉に込めた想いを知りたい」。
今回、そんな気持ちひとつで、作品の脚本・演出・出演まで手がける田中寅雄(たなかとらお)さんにお話を伺った。

日頃から脚本から演出、出演まで、マルチな表現を生業とする寅雄さん。
自ら舞台に立ち、そして数々の舞台を手がけてきた寅雄さんだからこそ見えた、伝わる言葉への気づきがあった。そしてそれが『生き逃げ』という「脚本を超える作品」につながっていったお話を聞かせてくれた。
使い回しの言葉は届かない
── ご自身が演じることと、脚本や演出で舞台をつくること。寅雄さんはどちらを先に始められたのですか?
寅雄 演じることです。もともとダンサーをやっていたけれど、俳優をやりたくなって、役者の道に。
その中で自分が演じているうちに、表現したいことがいろいろと出てきたんです。言葉の選び方とか、作品づくりに対して思うところがたくさん出てきて、「自分で作品づくりをやっていくんだろうな」と思い、俳優をやりながら舞台づくりを勉強するようになりました。
── なるほど。もともと言葉を紡ぎ、物語をつくることは好きでしたか?
寅雄 子どもの頃から物語をつくるようなことはしていましたね。
演出って「俳優をここから登場させて、音楽をこのタイミングでかけて、群衆がここから登場する」ということをしているわけです。つまり、究極に贅沢なひとり遊び。
僕は一人っ子なんです。だから子どもの頃、よくひとり遊びをしていました。キン肉マンの消しゴムを使って、ラジカセで音楽をかけながら戦わせたりとか。
── キン肉マンの消しゴムで(笑)。ものすごく凝ったひとり遊びですね。
寅雄 気づいたら、日常の中でも「もしもここからいきなり外国人が現れたら」とか「いま隣にあるガラスが割れたら」なんてことを想像するのが癖になっていて。
目の前の状況ありきで、「どんなことが起きたらドラマチックだろう」「そこで喋ったらおもしろそうな台詞はなんだろう」と考える癖がついたんです。

寅雄 だから僕、自分のことをあんまり作家気質とは思っていなくて。物語をつくりたいというよりは、まずシチュエーションがポン、とあって、そこから言葉が浮かび上がってくるんです。それを筋が通るようにいくつも紡いだ、みたいな作品が僕の手がけるものには多いと思います。
生き逃げもそう。そもそも台本がない状態で「じゃあまず、何やろっか」という状態から人が集まっていますから。
この作品は特に「寅雄カラー」みたいなものが出ていると思っています。自分が表現したいことを120%出そうと作った作品なので。すごく攻撃的な作品なんじゃないかな、と。

── 攻撃的な。
寅雄 そもそも僕自身、生き逃げを始める前までは、なぜか社会に対するフラストレーションを凄く抱えていたんです。
そこで、毎月新しい演劇作品、前衛的な作品をつくりはじめました。
それを4年ぐらい毎月やっているんですが、その中で脚本をつくる自分が言葉を雑に扱いそうになる瞬間があって。気を付けなければならないなと、本当に思ったんです。
── 言葉を雑に扱う、とは。
寅雄 誰かのために書いた言葉を、違う誰かにも使い回しすることは、言葉を雑に扱っていると思っています。そして僕自身もそれをやっていることに気づいたんです。
脚本家だけじゃなく役者でも、よく舞台の告知をメールで送るんですけど。みんなやりがちなのが、おなじ文面をテンプレで送ること。それって受け取った方は、「これは自分宛てじゃない」と気づくんですよね。
逆に、その人のためだけに書いた文というのは、「これは自分宛てだ」と思ってもらえる。やっぱり反応しちゃうじゃないですか、自分にまっすぐ飛んできたものって。
いかに丁寧な言葉であれ、その人に向けて書いた言葉には絶対に勝てないんです。
自分の言葉を重ねた先に、クラシックな言葉は生まれる
寅雄 そのことに気づいてからは、たった一人のキャラクターのためだけに台詞を書くことを意識しました。
たとえば『生き逃げ』には、死んだ兄の面影を引きずったまま生きる「オモカゲ」という囚人が登場します。

寅雄 そのオモカゲが劇中挿入歌『順風満帆』で、「ありのままにはかなわない。そう書いて『素敵』と読む」と歌うんです。
あれは、オモカゲのためだけに書いた歌詞だから、やっぱり他の囚人に歌わせるとハマっていないように感じる。
── 使い回しの言葉を使うと、言葉を受け取る側だけじゃなく、届ける側も違和感が出てくる。
寅雄 そうですね。
拙くても自分の言葉に変換した方がいいと思うのは、お話してきたように「届けたい人に届かないから」という理由もたしかにあります。けれどそもそも、自分の言葉で伝える方が、言葉を使っているその人自身が楽しいと思うんです。
戦争をテーマにした作品をやらせてもらっていると、インタビューなどで「先人の想いを」という言葉を当たり前のように使ってしまいがちなんですけど。
よく考えて使わなければならない言葉だと思うからこそ、毎回その言葉を当たり前のように使うことに、違和感を感じることもあるんです。

寅雄 だから「できるだけ自分で咀嚼した言葉で伝えるように」と後輩たちには常々言っていて。僕自身も台本を書くときから意識しています。
結局、自分の言葉の積み重ねでしか、宝物になるような言葉って生まれないので。
── 宝物になるような言葉、ですか。
寅雄 今、もう20年も続いている特攻隊をテーマにした舞台に携わっています。
20年の間に脚本もいろいろと変わってきてはいるんですけど、ずっと変わらない台詞もあって。それは使い回しの台詞ではないんですよね。時代が変わっても残り続ける音楽と一緒で、その言葉はもうクラシック、古典なんです。
そして古典になれるような言葉は、自分の言葉を重ねていく中でしか生まれない。
僕自身まだまだ、打ち上げ花火のように消えていく言葉を紡ぐのに精一杯だけれど。たくさんの作品を通して、その人にとって宝物になれるような言葉が生まれるのは、自分の言葉を重ねることからだと分かりました。
生き逃げは脚本を超えていく
── 生き逃げには、囚人たちが脚本を破って、一人ひとり胸の内を叫ぶシーンがあります。それも「自分の言葉で伝えることの大切さ」を訴えるメッセージになっている気がしました。

寅雄 あのシーンは毎回、演技なのか役者自身の本心なのか曖昧になるくらい俳優たちが全力で、再現性がない叫びをしているのですけど。
本来、俳優がああやって役の皮を剥ぎ取って舞台に立つことって、あまり良しとされていないんですよね。やっぱり演じることが、第一なので。
でも生き逃げでは、あえて演じることの不自由さを取っ払いたかった。俳優が120%のエネルギーを出し切れるような作品にしたかったんです。
それは僕自身、毎月脚本を書く中で「もっと違った表情を持つ言葉に出会いたい」という気持ちが高まっていたからでもあったし、信頼を置く俳優たちを集めたときに、彼らが一人ひとりエネルギーに満ち溢れていて「きっと何かを叫ぶんだろうな」という気配めいたものを感じたというのもあります。
── 寅雄さん自身は、『生き逃げ』は観る人にとって、どんな化学反応を起こすと考えていますか?
寅雄 どういうふうに共感してもらうかっていうのは、初演をやる前の稽古のときはすごく繊細に考えていたんです。だけど第二回公演の追加公演まで終えて今思うのは、「観る人への気遣いはいらないんだ」ということ。
とにかく圧倒させる、表現を浴びせることに僕たちが全力になって、その結果なにか残ったものに共感がついてくるだけなんだ、と今は思っています。
「登場人物の言葉や行動に観る人の何かが引っかかるように……」というのを繊細に考えすぎると、すごく収まりが良くなってしまうんですよね。誰かの評価に擦り合わせようとしていくと、舞台上で夢中に生きることができなくなる。
……ということを、「平均寿命」について考えていたときに、思って。

── 平均寿命?
寅雄 たぶん、平均寿命という言葉が浸透するまで、昔の人は「自分がいつまで生きるか」なんて考えなかったと思うんですよね。だからもっと目の前のことに夢中で生きれたんじゃないかと。
けれど今、平均寿命が「だいたい80歳くらい」とみんな思っているから、本当はその年齢まで生きれる保証なんかどこにもないのに、人生を逆算して生きている。そうするとやっぱり、「いくつまでにやっておかなければならないこと」をベースにした、薄い日常になっていくんじゃないかなと思うわけです。自分の「今この瞬間の気持ち」を置き去りにした日常に。
寿命を考えない生き方のほうが、命が燃えている実感はあるだろうなと僕は思っていて。そういう「滾(たぎ)る」感じは『生き逃げ』でも表現したいなと思っていました。
そうじゃないと、観る人を圧倒させることはできないんじゃないかと。
やっぱり演劇でお金をもらう意義として、観る人を圧倒させないといけないと考えていて。そうなったときに、もう俳優が脚本を超えるような作品をやろうと思ったんです。
── 脚本を超える。
寅雄 ふつう、作品にはプロデューサーがいて、演出家がいて脚本があって、俳優は脚本を超えられないんですけど。脚本を超える──あらかじめ用意された言葉を突き破るような作品をつくりたい気持ちがありました。
脚本をビリビリに破くシーンもそういう気持ちから取り入れて、叫びたいだけ叫んでもらって。俳優は「記憶ない」みたいになっているけど、いいんじゃないかと(笑)。それを成立させるためのライブハウスだから。
とにかく、ここまで自由に表現できる演劇って今までないので、自分でつくろうと思ったんです。またそれをおもしろいと言ってくれる俳優たちやスタッフ陣がいたのも、運命的でした。

言葉にも人の手のように、血が通う
寅雄 僕自身、演出家として俳優として、言葉で何ができるかの答えはまだ見つかっていないんです。それでも一つ思うのは、「言葉は人の手に似ている」ということ。
── どういうことでしょう?
寅雄 言葉って、使い方一つで誰かを殴る拳になることもできるし、誰かを包む手のひらになることもできる。残酷なものにも温かいものにもなれる。
そういう意味で、言葉は人の手に似ているなと思うんです。
人の手に似ているという点ではもうひとつ、言葉にも人の手のように血が通うことがある。
── 言葉に血が通う。
寅雄 俳優たちにはよく、言葉だけじゃなくて手のコミュニケーションを取らせるんです。
握手して台詞を言わせたり、マッサージし合ってもらったり。すると、言葉に連動して手に力が入ったり、あったかいものになったりする。それって、人の手に当たり前に血が通っているように、言葉にも血が通うからだと思っていて。

寅雄 ロボットじゃない人間が言葉を使う。
そこの違いは、血が通うかどうかだと思っています。そして、僕たちが生き逃げを通してできるのは、血の通った手のような言葉を表現していくこと。
どんなに字面が綺麗だったり有名だったりする言葉でも、受け売りや使い回しの言葉に血は通わない。その人自身の言葉に血は通い、それが人の心まで届いていくと信じているんです。
文/小山内彩希
写真/飯塚あさみ
画像・動画提供/ガチャ劇
作品情報
『生きることから逃げないために、あの日僕らは逃げ出した』
ライブインフォメーション
『第二回囚人博覧会 年末スペシャル 2DAYS』
12/28(土)2DAYS 初日「でっけぇでっけぇ夢を抱いた、小さな小さな檻の中」
12/29(日)2DAYS ファイナル「壁ぶち破ってブラジルまで」
OPEN 18:30/STRAT 19:00(2日間共通)
チケット料金 各日¥3,000(D代別途)
2Days通しチケット ¥6,000(D代別途)
チケットプレイガイド:eプラスにて発売中
一般発売 〜12/26(木)PM18:00