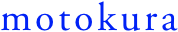この27年間の大半を、茨城県のとあるニュータウンでぼくは過ごした。
物心つく頃から友人の家の庭でトカゲを、近くの野原ではキジを探し回って遊んだ。
中学、高校にあがるとたくさんの熱帯魚を飼い、アクアリウムという名の生態系づくりに精をだした。
高校の入学祝いにねだったのは、らんちゅうと江戸錦という日本らしいおおぶりな金魚。
途中からオカメインコも我が家に合流し、いっしょに暮らしてきた。

高校を卒業する少しまえのこと、翡翠色にかがやく野鳥と出会った。
家から歩いてすぐの調整池に、カワセミの狩場であり住まいがあったのだ。
ほとんどの人が気づかず、見ようともせず素通りしてしまうけれど、夜明けとともにカワセミのつがいが、池を覗き見るのにちょうどいい岩場から突き出した枝に、必ずやって来る。
そして朝陽がさすのと同時に、夫婦はそろって歌いだす。
それは、彼らには彼らの世界があるのだと思わせるような幻想的な光景だった。

この体験をきっかけに、その調整池をマイフィールドと名付けて通うようになる。
その頃の自分は当たり前にあり続けると思っていた健康を失い、食べることも動くことにも制限があった。何に対しても前向きになれず、気持ちが沈みきっていた。
そんなときに出会ったものだから、はじめは現実逃避の対象でしかなかったかもしれない。だが、マイフィールドに通いカワセミのつがいの習慣や子どもの成長を観察していくうちに、さまざまな未知との出会いがあった。
いつしか心をふるわすことができる、前向きな自分を取りもどすことができた。

2018年の暮れに故郷のニュータウンを離れ、ドイツの首都ベルリンで暮らしはじめた。
この文章を書いている今、19世紀に建てられたアルトバウと呼ばれる古い集合住宅に住んでいる。
夜明けと夕暮れどきには中庭で野鳥たちが合唱し、ときにリスやうさぎが遊びにやって来るような環境だ。
いつものように中庭にあるお気に入りの椅子に腰掛けてノートに思うことを書き記していると、ふと思ったことがある。
それは、「心地よさには自然との距離感が影響しているのではないか?」ということだ。

ぼくは野に生きる隣人が好きだ。
しかし、この20数年のあいだに僕が育ったニュータウンでは、生物の住める自然がものすごいスピード感で失われてきた。
じっさいに小学生の高学年になる頃から、彼らと出会う機会も減ったように思う。
ぼくの目の届く範囲だけでも開発は今なお続き、野原に囲まれていた実家の周囲は、高校生になる頃までに開発し尽くした。
「もう野原を家にするのはやめたらいいのに」
祖母と母と、お茶しているときにポロッと漏れた。

しかし小学4年生だった頃のぼくは、野原だった場所にショッピングセンターが建つと聞いて、あたらしい遊び場ができることにワクワクした。一区画となりのあたらしい住宅地に、祖父母が引っ越してきたことも嬉しかった。
けれどたしかに、道端でよく出会ったキジ家族の住まいは、新興住宅の建設予定地にあった。
追い込まれた彼らはもう居なくなってしまったことを、僕は知っている。忘れもしないだろう。
生きものの犠牲に気づいて育ってきながら、このまま知らないふりをして生きていきたいだろうか…?

そんな生き方は、もうしたくない。
ニュータウンには、マイフィールドのような心に安らぎを与えてくれる自然がいまだ隠れるように存在する。
まだ在るからこそ、失われつつある心地よい距離感を自分の手で取り戻したい。そのために、どんな暮らしができるだろう。
自然を愛するベルリーナーに会いに行き、探ってみようと思う。
【心地よさと自然との距離感】#2| Maiaとの出会い に続きます。