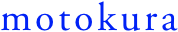赤や青のトタン屋根も、すっぽり雪に覆われる冬。
大きな青屋根のお家にひとり暮らす、おばあちゃんは言いました。
「いっぱい生きてからむしやってる、それだけや。昼間もやるし夜もやるし、いちいち片さねぇんだ。つないで糸にするんだ。ねじってつなぐのや──」
触れていれば自然と手が動き、長い冬のさみしさもこえてゆける。
からむしは、村のおばあちゃんたちにとって、その手に染みついて離れないもの。生きがいそのものです。

時折、お茶のみに遊びに行くと、「この冬は、ヒザも痛くて大変だったんだけど、ようやくこうして織りあがったんだよ」。たわいもないおしゃべりとともに、織り上げたからむし布(ふ)を目の前に広げて、見せてくれるのです。
手にしたのは一枚の布。そこには、この村に暮らす女性の人生がまるごと詰まっている。なんとかこの布を人目に触れさせて、活かすことができないだろうか──。
おばあちゃんの手から生まれた布に託して、昭和村のいとなみや佇まいを、次へとつなげていきたい。「渡し舟」の活動の根っこには、そんな想いがあるのではないかと私(筆者・中條)は思います。


渡辺 悦子さん(織姫8期生)
福島県出身。大学卒業後、東京でOL時代を過ごす。30歳までに「恋人のように愛せる仕事に出会いたい」という思いから20代後半で織姫体験生として村を訪れる。当初は1年の予定のところ、「からむし」に出会い、村に残ることを決める。これまでに日本民藝館展に作品の出展も行う。来村10年目で村の男性と結婚し、出産後も旦那さんの協力を得て、からむしの栽培と出荷に携わる。今では村内でも屈指の美しいからむしの引き手と認められる。

舟木 由貴子さん(織姫10期生)
茨城県出身。大学では染織を学ぶ。在学中から織姫事業のことを知り、卒業後は昭和村に行きたいと思っていたけれど、一旦就職をする。デザイン関係の仕事に従事したのち、織姫事業のことを思い出し「やりたいことをやろう」と、織姫体験生として村を訪れる。現在は3児の母であり、国の選定保存技術にも指定される「からむし生産技術保存協会」の事務局員として活動。正当な技術の継承のために奔走する日々。
からむしを通した恩返しとしてはじまった、「渡し舟」の取り組み
「渡し舟 ─わたしふね─」は、元織姫(からむし織体験生)の渡辺悦子さんと舟木由貴子さんのユニット名。名前はふたりの名字にちなんでつけられました。また、そこには、「からむし」を通して、村の内と外をつなぐ渡し舟になりたいという思いも託されています。
取り組みのひとつとして、2015年6月に、渡辺さんの自宅の一室をしつらえた完全予約制のお店をOPEN。
からむしを身近な暮らしに合うように、村のおばあちゃんたちが織り上げた布に手を加え、製品として販売を行っています。また、販売を通じてだけでは伝わりきらない、からむしの魅力を知ってもらうためのお話会やワークショップも各地で開催しています。

渡し舟のおふたりと知り合って早2年。私が初めて村を訪れたときから、折に触れて対話を重ねてきました。そんな彼女たちが、あるとき困ったように言いました。
「この村のひとたちのいとなみを、お金のやり取りにはうまく置き換えられないんだよね」
結婚し家庭を築き、村の人となったいま、「からむし」やこの村の「いとなみ」をふたりはどのように伝えていこうとしているのか。活動をはじめて感じる難しさとは何なのか──。
今回初めて昭和村を訪れた、灯台もと暮らし編集部の小山内彩希さんとともに、お話を伺いました。

── 2015年に活動をはじめたという「渡し舟」ですが、ふたりで活動を行うことになったきっかけを教えてください。
舟木 体験生のときは住居もあてがわれるし、教えてくれるおばあちゃんたちもかわいいし、大好きな織物も思う存分にできて、私、今死んでもいいわっていうくらい、こんなに幸せなことはないと思う日々でした。それくらい、当時はとっても軽い気持ちだった(笑)。

渡辺 なんかとにかく楽しかったのね。共同生活とかも、おばあちゃんたちとのお茶の時間も。ただそれを毎日楽しんで。1年目は先のこともあんまり考えてなかったかな。
舟木 当時は、先輩の織姫さんから厳しく「(からむしの技術にしても)簡単に教えてもらえるものではないんだよ」と、言い聞かされて。
そんな教えもあって、1年の体験が終わる頃には、からむしや織物をやりたいようにやらせてもらえていた自分が、とにかく村に感謝するようになっていた。お礼をしてもしきれないけど、なんとかお礼したい!という思いから、からむしを通した恩返しをしていきたいと思うようになりました。

── 具体的には、どんな風に恩返しをしたいと思うようになったんですか?
舟木 からむしをとりまく環境が、もっと良くなればいいなと思ったのね。「からむし」について、ひとりでも多くのひとに知ってもらいたいし、村のひとたちには、これほどのものを守りながら、今もつくり続けていることをもっと誇ってほしかった。私の独りよがりかもしれないけれど、からむしを知る人が増えれば、村のみんなもいまよりもっとからむしを好きになれるんじゃないかと思って。
ご縁があって、この村のひとと結婚して出産を経験したことも、私にとっては大きな変化だった。それまではからむし単体でしか見えていなかったけど、村のひとたちに全面的に支えられている実感を持つようになったんだよね。腰を据えてやっていこうと思えるようになったのはそれから。
そんななかで、からむしを通して昭和村に来た私たちにできること──村の内と外を、からむしを通してつないでいくこと──をしていこうとはじめたのが「渡し舟」。

製品を販売し、売り上げたお金は、布を織ったおばあちゃんに還元していく

── もともとおふたりは、仲良しだったんですか?
渡辺 気は合いましたね。日頃から、こんな風に問題意識の共有もしていたので、自然と。
たぶんこれから先、もともと栽培してきた家の誰かが継いでいくという流れは見えてこないのが現実です。
だから織姫を経て村に残る私たちがつないでいる間に、村の中でも「昔じいちゃんがやってたからやってみようかな」、というひとが現れてくれたらうれしいと思って、ふたりで何かしようよということになって。

── 体験生のときから2、3年と過ごす中で、からむし自体の見え方が「楽しい」「綺麗」から、違う感覚になっていくんですか? からむしを「なんとかしていきたい!」という思いに変わったり。
渡辺 そうですね。最初はからむし単体として「綺麗だなぁ、美しいなぁ」だけなんだけど、だんだんそこに費やされた労力とか想いまで、伝わってくるようになりますね。畑の始末ひとつにしても、手がかかっているなと。一生懸命な姿も見ているから、3、4年過ぎる頃には全然重みが違ってきます。

── 例えば畑に火入れをしている姿を見たとき、現象として目の前にあるのは畑で、布も出来上がった「もの」だと思います。でもそうではなくて、その背景の年月が織姫さんたちには見えてしまうのですか?
渡辺 全部がつながって見えちゃいますよね。
── 全部がつながったものとして、出来上がった布を見たとき、それは「いとおしい」という感覚になるのか、ちょっと想像すると、「こわい」と思う瞬間もありそうですね。
渡辺 預かるのはこわいですよ、やっぱり。ハサミを入れるのもこわいし。おばあちゃんは、織り上げた布を「お前たちの好きにしていいぞぉ」と渡してくれるけど、よくよく考えるとこわいよね。
これだけ手間ひまかけて出来上がったものをと思うと。自分自身で引いた繊維に対して、こわいという感覚はないけど、出荷するときに寂しい感じはありますね。あぁ、行っちゃうのかぁって。

生きている「実感」を求めていたんだと思う。からむしに関わって生きていくということ
── おふたりが織姫体験生として村に来たのはいずれも20代後半。女性にとって、自分の人生に迷う時期がその頃なのかなと、実感することも多いです。舟木さんが「やりたいことがやれるから昭和村に来た」というのは、どんなことだったのですか?
舟木 私にとっては機織り。それが自分にとっての最高の仕事だと思っていたけれど、大学卒業後は違う仕事につきました。忙しくて自分らしさがなくなっていると感じたときに、本来の好きだと思えることをやりたい!と思い出して。
矛盾しているようだけど、機織りで食べていけるわけではない昭和村を選びました。私がなりたかったのは、職人ではなかったから。自分で好きなものづくりができそうな昭和村に惹かれて、行ってみようかと。
渡辺 みんな、そんなに覚悟を持って来ていなかったと思う。それだけに織姫たちは、この村で何年か暮らしていくうちに、来たときとは考え方が大きく変わっていくし、みんな、打ちのめされるんだと思います。
── 初めてお会いしたときに、渡辺さんは「恋人のように愛せる、自分が胸を張ってできる仕事に出会いたかった」と仰っていて、すごく印象的でした。なぜ、そう思うようになったんですか?
渡辺 仕事と生業という言葉は微妙に違うんだよね。私が求めていたのは、食べていく方じゃなくて、一生付き合っていけるものとしての「仕事」だったのね。生業は「生きていく業」と書くでしょ。食べていくのはそっち。
── 渡辺さんがしたかったのは「仕事」だった?
渡辺 だったんですね。それで食べていけるとか度外視で、私が一生付き合っていける、生きながらやっていけることが欲しかったんだと今では思います。くさくいえば生きている「実感」を求めていたんだよね。
そこで食べていけたら良かったけど、食べていけるかどうかと天秤にかける前に、とにかくやりに来ちゃった。


── やりに来ちゃったらそうだった?
渡辺 仕事としてはね、とにかく夢中。もう引き込まれるものがありました。ただ、お金を稼ぐという意味で、食べていくのは難しい。そうやって整理して考える前に、季節ごと作業の内容も変わっていくし、気がつくと、次の年のからむしのことを考えていましたね。
舟木 今、普通の生活って、通勤電車に乗って職場に行ってお金を稼いで、必要なものはお金を出せば手に入る仕方で毎日が回ってる。でも、もうちょっと人間くさい生き方というのが一方にはあるはずで。
そちらに惹かれる人も、多くなってきているのかな。暮らしのなかからものが生まれて、それが生活の一部になっていく暮らし。私たちは、昭和村でからむしに関わりながら生きていて幸せなんですね、すごく。それってみんなもそうなれるよね?という思いを届けたい。

小山内 昭和村では、そんな当たり前が当たり前のままにある。でも本来それってすごいこととか難しいことではないという感じでしょうか?
舟木 そうそう。本来すごいことでもなくて、ここ最近そうしていないというだけ。ずっと長い間、人間はそうやって暮らしてきたと思います。
渡辺 都会だと、なにかしらお金で解決できて、自分が深く関わらなくてもなんでも成り立っているように見えるでしょ。でもこういう場所だと、自分が関わっていかないと回っていかないからね。
── 実感が持てることが大きいのでしょうか?
渡辺 関わって生きていくということかな。消費していくことだけでは私は満たされなかった。たぶん関わり方の問題だと思うんだけど。
舟木 それこそ1期生の頃、村のなかには「何でからむしやってんだ?早く帰れ」という姿勢のひともいたと先輩からよく聞きました。
本来は換金作物で、良いからむしをつくるために技術の継承は家ごとに門外不出のものだった。けれど村中での継承が難しくなってきて、一生懸命にからむしに向かう織姫さんたちに、村のひともだんだん教えてくれるようになっていった。

舟木 今では「からむしやめろ」というひとはほとんどいないです。織姫が来ることによって、村のひとたちの意識も自然と変わっていったと思います。そんな風に、外から来る風によって、からむしを取りまく環境が変わることもたくさんある。その一端の役割を私たちが担えればいいなぁと思います。
お金にならないから「からむしでは食っていけない」ではなく、大してお金は稼げないけど、田畑を耕して自然とともに暮らせばここなら生きていくことができる。それは一見、馬鹿なことに見えるかもしれないけれど、こうしたいとなみを村の外のひとたちに知ってもらうだけでも、次の世代にとって、新しい兆しになっていくんじゃないかな?
「なんでもいいんじゃないんだぞ」。師匠のおじいさんから受け継いだことば
── 織姫として数年過ごすうちに、布が生まれてくる背景を含めて「この村で暮らしたい、からむしを継いでいきたい」と思うようになっている。一方で、からむしを使った「もの」として、なかなか出口が見つからないという話も伺います。織姫を経験された方の中には作家として活動していく人や、いろんな形でものづくりをされるひとがいると思います。お二人はどんなカタチを目指しているのか、教えていただきたいです。
舟木 私たちは、作家になりたいわけではないから。からむしの持つ品格とか、そこに費やされた歴史や想いを含めて伝えていきたい。だから可愛らしくてアイコニックなものづくりにはなっていかないかな。でも、「からむし」という言葉は、小学生にも知ってもらいたいので、一人でも多くのひとに伝えたいと思ったら、それも大事だと思います。
渡辺 もう素材のときの説得力がじつは一番で、手を加えれば加えるほど離れていくというか。その良さをどうやって「もの」に出すか、そこが本当に難しい。やっていくなかで感じるのは、この布が持っているボリュームとか、織られた布そのものの力を無くさないように、ものづくりしていきたいということだけ。
── からむしに出会うきっかけとして、いろんな入り口と幅があることも大切ということでしょうか?
渡辺 つまり「何でもいいんじゃないんだ」って、よく師匠のおじいさんに言われたの。私たちも、そういう気持ちでやることが大事だと思う。素材としての良さを引き出した、いいものをつくらないと。
ただ、ほんとうに大事なのは、どういう見せ方かというよりも、昭和村でからむしが続いていくためのサイクルがちゃんと巡っていくこと。

── 換金作物としては、100匁(もんめ)の束に束ねられた「からむしの繊維(*1)。」が昭和村での完成ですよね。素材のままでもすごく美しい。糸や布にする前の状態で、外に出すということも考えたりされますか?
(*1)からむしの繊維:その昔、新潟から買い付けに来る人はこの状態を「青苧(あおそ)」と呼んでいた。
舟木 でもその価値をわかる人っていますか?
── それはしっかり糸になって、布になって、使われていくことがからむしにとっての幸せで、単に飾られて一定の時間を楽しんでおしまい、というものではないという?
舟木 まぁ一瞬、そういうことはあってもいいかもね。美しいと思います。でも、美しいときには限りがあるし、その美しさがどうして出てくるのか。単に消費されて捨てられてしまうのであれば、そんな扱われ方はして欲しくないかな。

渡辺 ものとしての幸せね。
舟木 使われないと、人間じゃないもんね。どんなに美人な子だって、飾られているだけじゃなくて悲しんだり喜んだりして生きているわけだし。
── そうなると布として「使われる暮らし」が回復されないと、せっかく布になっても活きてこない。でも、その布の使いこなし方を私たちは知らない。そこを知りたいと思うひとも増えているかもしれません。そういう暮らし、この布を使いこなせる暮らしが昭和村にはあるから、訪れてしまうということもありそうですね?
渡辺 そうしなきゃいけないですよね、これから。結局この美しさが生まれたのは、上布という活かされる道があって、そこを目指してこの美しさになっていると思うんですよ。
舟木 越後上布・小千谷縮(*2)。という新潟でつくられる着物の材料として。新潟からからむしの繊維(青苧)を買いに来る新潟方面とのつながりがあって、それで昭和村のからむし栽培は残ってきた。
(*2)越後上布・小千谷縮:国指定重要無形文化財・ユネスコ無形文化遺産。古くより新潟県魚沼地方で手がけられ、上布の中でも最高級のものとして知られる。
渡辺 昭和村のからむしの美しさは、追求した結果の姿。工夫してきたと思う、いいものをつくるためにこの方がいいとか。「何でもいいんじゃないんだぞ」というのはそういうことだと思います。そこが崩れていくと、ひとの心を打つようなものって出来てこない。
その時代は上布というゴールがあったから良かったし、出来上がったもの自体も、生活の中で生き生きとしていたと思う。まぁ現代は、そういうゴールが見えなくなっているので、そこを探していかないとダメですね。

── これだけのものを活かしていける、今の暮らしにあった道。
渡辺 多分上布じゃなくてよいのなら、ここまで洗練したものを必要としなくなっていくんじゃないかな。
── そうなると、村の中で「もの」としての出口を探り続けると同時に、これからも越後上布や小千谷縮として残っていってほしいですか?
渡辺 それもあって当然だと思う。そうでなくちゃこの素材の意味がないというか、簡単に到達できるものではないというか。最終的に活かすところも高みを目指していかないと、理屈抜きに感動するものはできないんじゃないかと思います。上布に限らず、この素材が活かされていく場所を探していかないとですね。
── 「からむし」という言葉を知って、どんな風に手をかけて育てられ、織り上げられているか。背景を知る機会が増えることによって、一枚の布があるだけで、その凄さを感じられるひとも増えるのかな?と思いました。

渡辺 そう思う。私はそういうところを目指したい。もうこの布があるだけで、「わぁすごい!」「これはいいものだ!」って伝わってくれる世の中。そうなれば、手に取りやすいものばかりにいかなくても、布そのもので手元に置いてもらえるようになるのかなって思うんだけど。

渡辺 でもそれは織物全体の課題だと思う。まず、回っていくことが大変だよね。特に靭皮(じんぴ)(*3)。という植物の繊維を、「績む(うむ)」という形でつないでいく。こういうものって本当に、生産性があまりにも悪くて……。
(*3)靭皮(じんぴ):植物の表皮のすぐ内側にある繊維。亜麻、大麻、苧麻など、いわゆるアサの靭皮は細くてやわらかいのが特徴で、古くより衣料に用いられてきた

木綿(2〜3cm)などの短繊維は「紡ぐ」といい、からむし(約1.5m)など長繊維は「績む」と使い分ける
丸腰で来るから、受け入れてもらえる場所
── 少し飛躍してしまうかもしれないのですが、今後のからむしと昭和村の暮らしを考えたときに、外のひとたちに買ってもらうだけではなく、この村に暮らしているから、からむしを身につけて使っていくことができる。で、それを使いたいのであれば、この村で暮らしていく。といった逆転の発想があってもいいのかもしれませんね?
舟木 もうそれしかないです。ただ、ここでの生活が長くなるうちに、意外と村のなかにもからむしのことを、知らないひとも多いと気づかされて。それではほんとうの意味で、「昭和村のからむし」とは言えないんじゃないかって。
渡辺 村のひとたちにとって、からむしは、製品化されずに原料として出荷されていくもの。それはお金に代わる大事なものとして教わってきているから、長い間、自分たちのために使うものではなかった。でもこれからは、残すためにも自分たちの生活に取り入れていくことも必要と思う。そうした部分を村のひとと一緒に考えていくことも、今後の「渡し舟」の大事な取り組みだと思います。

渡辺 渡し舟はふたりで始めたけど、できるだけ協力者は増やしていきたいと考えていて。村のひとにもどんどん関わってもらって、ほかの織姫さんとも、何か得意なことを活かして協力し合えたらうれしいですね。
小山内 生活のあちらこちらでからむしを身につけて暮らしている風景がかっこよくてそれが目に見えたら、説得されてしまう気がします。からむしを育てて、糸をつくって、織りをして、しかもその布を身につけて暮らしている風景。
── そうなると、からむしのある昭和村の風景も水も土も、畑も守っていかないと、そうした暮らしは続けられない気がします。
舟木 もうなんか、現代社会と戦ってるよね(笑)。できると思いますか?私たちの時代には難しいかもしれないけれど、子どもの子どもくらいの時代には、そこに近づいていればいいなぁくらいの感じかなぁ。
小山内 からむしは否定しようもないな、と思いました。間違っていることはひとつもない。

からむしの全ては循環していく
渡辺 今それで思い出した。ある木工作家さんに言われた言葉。「正しさだけではひとは動かせないよ」って。もっとね、単純に。いいなと思ってもらえるものであったらいいって。元来は単純なことなのに、今のシステムに合わせようとするとすごく難しくなっちゃうんだよね。とにかく長い間続いてきたものを、ここで無くしてしまう怖さ。やっぱり一度消えてしまうと、わからなくなっちゃうみたいで。
── 単純に「いいな」と思ってもらえる「もの」であり「暮らし」。そういう場所としての昭和村であり続けてほしいという気持ちでしょうか?
渡辺 私たちが織姫として来たときに、いいなと感じたように、感じられる場所であり続けたらいいのかなって。そこを自分たちがちゃんとやらないと。
小山内 開くというよりもまずは守る? この村に脈々と続くいとなみと、循環している流れが透明であるために、守っていくというような……?

舟木 そうですね。昭和村のひとたちがつなげてきた生活も含めて、からむしのあるこの村の暮らしを、守りたいかな。
渡辺 そこの部分が揺らいじゃうと、何も開かれていかないと思うので、軸の部分は守る。自分のやり方を持ち込んで通すのは、ここではちょっと違うかな、と思う。
── 昭和村に来るのであれば、郷に従う方がいい?
渡辺 織姫は自力でなんて生きていけないから。村のひとたちみんなに助けてもらうしかないんだよね。雪もすごく大変だし、この村のおじいちゃんおばあちゃんは、女の子がこんなところで生きていくのがどんなに大変かっていうのを知っているから。
舟木 だから、感謝もするし。
渡辺 村もそういう子たちが来るから、「面倒みなきゃなんねぇ」と一生懸命になってくれる。それがいいのかもね。丸腰でくるから、受け入れてもらえる。

糸績みといとなみは、よく似ている
大きな青屋根のお家に暮らすおばあちゃんは、ことし92歳になるそうです。
まだ糸績みを見たことがなかった私に「こんなの簡単や」と、その技を見せてくれたのは、昨年の年初めのことでした。
繰り返し、繰り返し。「誰がやっても一緒や。結ばずに、ねじってつなぐのや」。そう言いながら、みるみるうちに、おばあちゃんは短かい繊維を口にふくんで手先へ通し、するするするする、糸につなげていくのです。
「糸績みといとなみは、よく似ている。」
この村に生きてきたひとにとって、ひとりの力で完成することはひとつとありません。
結ばずに、次へ次へとつないでいく。
おばあちゃんの手によって績み出される一本の糸。それはまるで、この村に暮らす人たちのいとなみそのものと呼べるのではないか。
渡し舟の活動も、そうして次の人へつないでいく糸績みのようだなぁ。今回お話をまとめながら、そう思うようになりました。
昭和村のからむしのこと、いとなみのこと。もっと深く知っていきたいと思ったら、まずは「渡し舟」を訪ねてみてください。
事前の予約を、忘れずに。
「渡し舟」のFacebookページはこちら。

今年もすでに、平成30年度(第25期)の「からむし織体験生『織姫・彦星』」の募集が始まっています。募集期間は10月31日まで。
(この記事は、福島県昭和村と協働で製作する記事広告コンテンツです)
文章:中條美咲
編集:小山内彩希
写真:タクロコマ(小松﨑拓郎)、伊佐知美