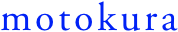ダンス、演劇、音楽劇などのパフォーミングアーツが好きな私(編集部・立花)が掲げた問は、「私はアートで救われるのか」。「私は何者なのか」という不安や焦燥感、そして「何を言ってもどうにもならない」という社会のぼんやりとした諦めと閉塞感から脱するために、アートが今できることや、アートが必要な意味について、学びます。
『灯台もと暮らし』の裏番組である「もとくらの深夜枠」という有料マガジンで、私はライターの中條美咲さんと一緒に「待てない男女」という連載を書いています。
この連載の始まりは「結婚はそもそも必要なのか」と疑問に思ったことがきっかけです。当たり前だと思っていたことが、当たり前ではないかもしれないと気付いた時、世界がパッと開けると同時に、戸惑いや葛藤が生まれます。
ただ、私はこの当たり前と当たり前じゃないものとの境目を越えていく手段やきっかけに、アートは大きく関わるのではと思っていると同時に“救い”になるのではと感じたことが何度かありました。
ディレクターの市村作知雄さんは、国内でも指折りの規模を誇る舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー(以下、F/T)」で、「境界を越えて、新しい人へ」というコンセプトを掲げました。
そのコンセプトの真意と、市村さんご自身がアートに対して“救う”“救われる”以外に見出す希望と価値を、伺います。
(アイキャッチ:アジアシリーズ vol.3 マレーシア特集 公演編 インスタントカフェ・シアターカンパニー『NADIRAH』の様子 公式サイトより Photo: 青木司)
救う・救われるという考え方は好きじゃない
市村 作知雄(以下、市村) 取材依頼書を拝見しました。
── ありがとうございます。「アートで“私”は救われるのか」という抽象的な問いなのですが、私自身のアートに対する向き合い方は、2010年のF/Tに影響を受けている部分があるので、市村さんに取材を申し込ませていただきました。

市村 依頼書の文面から、あなた(編集部・立花)には、かなり閉塞的な、どこにも動きようのない世界が見えているのかなと感じました。もう世界は動かない、変わらない、と感じているのかなと。
(中略)発言をしてもすぐに叩かれつぶされてしまい、表現物が喰らい尽くされる(消費される)ような気もします。事実、私は何をするにも何を言うにも、無意識のうちに誰かの顔色を伺い、答えを求めてしまっています。
「何を言ってもどうにもならない」という諦めと閉塞感が漂う今、それから脱するための「救い」は、芸術に託された役割であってほしい。その「救い」が食いつぶされないために、作り手ができること、また食いつぶさないために受け手ができることは何かを考える特集を作りたいと考えております。(立花から市村さんへお送りした依頼書の一部)
── そうかもしれません。ただ、その閉塞感に風穴を開けてくれるのがアートだと感じて「アートで“私”は救われるのか」という問にしたのですが、その点はいかがですか。
市村 僕は基本的に救う・救われるという考え方はとっていません。というか、あんまり好きじゃない(笑)。なぜなら、救う側と救われる側が出てきて、誰かが受け身になるようなニュアンスを感じるからです。
── うーん。
市村 少なくとも僕は、アートが主体的に直接的に誰かを救うということはないと思っています。でも、いろんなことを考えるきっかけにはなる。僕がそう考えているということは、取材の前にお伝えした方がいいかなと思いました。
── かしこまりました。では、救うか救われるかの是非ではなく、私のような閉塞感を抱える人々に対してアートは何ができるのかということを、市村さんにはお伺いできればと思います。
現代の若者に、世界はどう見えているんだろうか
── 2016年10月15日から12月11日まで東京都豊島区を中心に開催されていたF/Tのコンセプトは「境界を越えて、新しい人へ」でしたが、改めてこのコンセプトにされた背景を教えてください。
市村 僕がF/Tのディレクターに就任してから、テーマに“境界”という言葉を3回使っています。2014年は「境界線上で、あそぶ」、2015年は「融解する境界」でした。これらは「境界を越えて、新しい人へ」への伏線で、最終的にたどり着きたかったのが今回のコンセプトです。
── 市村さんが、“境界”にこだわるのはどうしてなのでしょうか。
市村 世代や国の境界はどのように生まれ、またどのように越えられていくのかということが、僕が今、一番知りたいことだからだと思います。
── なぜそれらのことを知りたいと思ったのですか。
市村 日本での世代間ギャップが非常に大きいと感じたことが影響しています。

市村 あなた方(編集部・立花とタクロコマ)のような若いひとたちは、20年後には世界を引っ張っていくような存在です。あなた方は僕にとっては、コンセプトにもある“新しい人”でもある。では20年後、その“新しい人”であるあなた方は一体何をするのだろうかということに、僕は興味があるんです。
「現代の若者に、世界はどう見えているんだろうか」。こうした疑問が生まれ、世代間ギャップを感じるようになった理由は、歴史的背景によるものだと思っています。
── 歴史的背景というのは、具体的にどの時代のことでしょうか。
市村 あなた方の時代の両親は、第二次世界大戦後に生まれた世代でしょう。親がすでに戦争というものに対する実感がないから、若い世代も日常から戦争が切り離され、はるかに遠い存在として認識している。話題にも上がらない。
一方で、コンピューターやネットは自分の体の一部のように使うことができる。その世代間で、一つの境界ができているんじゃないかと、僕は思うんです。「戦争を知らない」という、とてつもなく大きな非体験を共有している世代からは一体何が生まれるのか、僕は知りたい。
あなたはアジアのことをどれくらい知っているか
── 国同士の“境界”は、どんな時に感じられましたか。
市村 F/Tでは、2014年からアジアシリーズと題して、韓国(2014年)、ミャンマー(2015年)のそれぞれのアーティストたちを招聘(しょうへい)して作品を上演しました。僕自身、彼らと一緒に作品をつくる中で「同じアジアなのに、僕はアジアのことを何も知らない」という事実に打ちのめされたんです。
同時に、僕らには到底理解できない歴史を抱えているということも学びました。
── 具体的にどんな歴史的出来事に関して、そう感じられたのでしょうか。
市村 例えば、フィリピンは約400年間スペイン、それからアメリカの植民地として民族間の衝突が繰り返されてきました。日本は、フィリピンを含め他国を植民地化したことはあるけれど、我々が支配されたことはない。ましてや400年以上他の国の領土となっていたという事実は、今を生きる僕らがどんな豊かな想像力を駆使しても、理解できないんです。だって、日本に置き換えれば、江戸時代くらいからスペインに占領されていたということですからね。想像できますか?
── ……いえ、できないです。
市村 今回のF/Tのアジアシリーズでは、マレーシアのインスタントカフェ・シアターカンパニーを誘致し『NADIRAH』(ナディラ)という作品を上演しましたが、この中でもマレーシア特有の宗教や民族間の問題が扱われていました。

── 『NADIRAH』は私も観劇しましたが、マレー語と中国語、それから英語が混在しながら日常会話されていることに驚きました。親子や友達同士で、英語やマレー語が混ざって会話するというのは、今の日本では考えられないことですから。
市村 そうですね。マレーシアが独立したのは1957年で、しかもその背景には多くの人々が虐殺された出来事があります。日本では戦争経験がない世代が多数になってきている一方、マレーシアでは当時をよく知る第一世代がまだ現役なわけです。我々の想像力では到底及ばない歴史を、アジアの国々は抱えている。けれど、そういう歴史について我々はほとんど知らない。僕も、アジアシリーズを始めたここ数年間は、各国の歴史や政治をずっと勉強して現地の役者や演出家たちと話して、ようやく知り始めました。

── 観客は、役者や演出家たちと直接話せるチャンスがありません。F/Tではトークイベントなどのプログラムもありますが、作品だけ見て、その感想や気づいたこと、作品の制作背景などに触れる機会はよほど積極的にならないと得ることができないと思います。こうしたトークなどに参加する方々は、むしろ“知らない”ということに自覚的だと思うのですが、『NADIRAH』をはじめとするアジアシリーズの作品一つひとつを通して、市村さんが観客に期待することというのはどんなことですか。
市村 日本がアジアや世界についてどれだけ知らないか、自分たちの国がどれだけ特異な歴史を経てきたかということに、まずは気づいてもらえたらいいなと思いますね。例えば、韓国で結婚したら苗字がどうなるか、知っていますか?
── うーん……知らないです。
市村 苗字は、変わらないんですよ。子どもは父方か母方か選択できるんです。台湾も韓国と同じで変わらない。日本に置き換えれば誰しもが知っていることなのに韓国の事情となった途端、分からなくなる。こんな風に僕らの常識が通じないことなんていっぱいあるのに、全然知られていないんですよ。
── ただ、私は「NADIRAH」を通してマレーシアの歴史の一部を垣間見ることができました。だから、やっぱり演劇やアートが“知らない”ことを気づくきっかけにはなりうると思いますね。
安心できるエンターテインメントと、不安に駆られるアート
市村 “知らない”ことをテーマに扱う作品を主体的に観に行くことは、残念ながら今の日本ではなかなか根付いていません。演劇を含めた現代アートって、日本ではどうしてもお客が入らない。エンターテイメントとアートの違うところは、そこです。エンターテイメントは、確認をしに行く作業だと、僕は思っているんですね。
── どういうことでしょうか。
市村 たとえばルーヴル美術館の「モナ・リザ」に、どうしてあんなにひとが殺到するかというと、「ああ、本当に教科書通りの絵なんだ」ということを確認できるからだと思うんです。すでに見たことのあるものを見せるアート、確認するためのアートというのは、お客を集めます。なぜかというと、もう知っているものを確認する作業には、予期せぬものがあるかもしれないという不安がないからです。話の筋や結末とか、作品の見た目とかみんな知っているから安心して見に行けるんです。
でも現代アートはそうはいかない。初めて観る時は「この見方でいいんだろうか」「作者はどんなこと考えているんだろうか」と不安を抱えつつ観るものが多い。
日本はそういう、不安を覚えるアートにはお客が入らない。我々がやっているものは、決して安心しては観られないから、なかなか難しい部分もあります。
── 現代アートは、おそらく時代が変わっても、どうしても不安感の強いままな気がしますし、それが“現代アート”と呼ばれる所以のような気もします。本当はたくさんの人に観てもらえたら、という気持ちもありますが……。
市村 それは、分からない。アートのつくり手も観客も、少しずつ世代が変わっている。去年のF/Tのテーマに掲げた“新しい人”の時代になるとアートに対する考え方も変わるかもしれません。
多様性という言葉ではくくれない“新しい人”の時代が来る
── 最後に、その“新しい人”の可能性とアートとの関係を教えてください。
市村 僕の世代から見ると多様性という言葉は、いろいろな考え方や価値観を学ぶ上で重要なんだけれど、もう多様性という言葉すら意味をなさないような時代が来ると思っています。あなた方のような世代も、その時代を生きる“新しい人”にあたるかもしれない。
例えば、先ほど出てきたマレーシアでは移民を受け入れてきた歴史上、中華系やマレー系、インド系など呼び方が分かれているんだけど、“新しい人”の時代になればそういった発想そのものが古くなっていくかもしれないということです。
── そうですね。
市村 マレーシアに住んでいる中華系の若いマレーシア人に中国に戻ることはあるのかと聞くと「戻ったことはない。僕の先祖が中国のどの地域から来たのかも分からない」と言っていました。
じゃあ彼は、一体いつまでチャイニーズと呼ばれるのか? 日本人も、日系3世とか4世と呼ばれるひとたちがいるけれど、彼らはいつまでそう呼ばれ続けるのだろう?
F/Tのプログラムを通して、いま多様性と呼ばれているものの、その先を見たいと思ったんです。
── “新しい人”たちが第一線で活躍する時代になれば、私が今、漠然と感じている閉塞感は消失しているのでしょうか。
市村 それは分からないですね。ただ、日本の今の政治体制が1000年後にも通用すると思います?
── いえ、想像できないです。
市村 そうでしょう。きっと、どこかで変わるんですよ。でもどう変わるかというビジョンがない。だから、閉塞感が蔓延してしまうし、世界はもう変わらない、あとは壊れるだけだという考えになってしまう。
僕が育った時代は、ちょうど資本主義のアメリカと社会主義のソ連が対立していて差別意識が強かったし、日本でも中国人や韓国人を馬鹿にしているひとは珍しくありませんでした。そういう情勢の中で育った僕らと、当時の国同士の対立や戦争への実体験が消えてしまった時代を生きている若い世代とでは、見えている世界が違う。ここ70年くらいで、劇的に世界は変わってきた。
“新しい人”には、一体今の世界はどう見えているのか。その世界で、どうやって生きていけばいいのか。アートはそれらの答えを与えてくれるわけではないけれど、示唆はしてくれると思います。
── 現時点で、市村さんは今の若い人に世界はどう見えていると推測していらっしゃいますか。
市村 かなりのっぺらぼうの世界が見えているんじゃないかと類推しているんだけれどね。境のない世界が見えているような気がするけれど、どうなんだろう。これはきっと、生きている以上ずっと考え続けることだと思うし、アートが好きかどうかにかかわらず個人でも是非考えてみてほしいですね。

お話をうかがったひと
市村 作知雄(いちむら さちお)
フェスティバル/トーキョー・ディレクター。1949年生まれ。ダンスグループ山海塾の制作を経て、トヨタ・アートマネジメント講座ディレクター、パークタワーホールアートプログラムアドバイザー、㈱シアターテレビジョン代表取締役を歴任。東京国際舞台芸術フェスティバル事務局長、東京国際芸術祭ディレクターとして国内外の舞台芸術公演のプログラミング、プロデュース、文化施設の運営を手掛けるほか、アートマネジメント、企業を文化を結ぶさまざまなプロジェクト、NPOの調査研究などにも取り組む。現在、NPO法人アートネットワーク・ジャパン会長、東京藝術大学音楽環境創造科准教授。