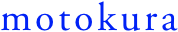人里離れた、森のなか。
森は、動物と人間の世界のさかい目。
考えごとがあるときは、その境界線を歩きながら、木の実が落ちる音、風が凪ぐ音、落ち葉を踏みしめる自分の足音に耳をすます。
北海道の下川町という、まちの9割が森に囲まれたこの土地に、わたしが足を踏み入れてからずっと問いつづけていることを、反芻しながら。
「“編集”って、なんだろう」。
誰も答えを知らない。教えてくれるひとだって、誰もいない。
でも、だから、おもしろい。
ダイナミックに変化する北海道の大自然に見守られながら、ここで何ができるのか。どう生きるか。
果てしない編集の大宇宙へ飛びこんだ編集者・立花の、ポツリ、ポツリとこぼす、考えごとと、ひとりごと。
***
「編集者は裏方であるべし」という思いは、このお仕事をするようになってから基本的には変わっていない。
けれど、裏方だからといって、無理に人目につかないように避ける必要もないと、今は思っている。
“編集”には、意思があるから。
どんなに隠れようとしたって、むずかしいように感じる。

たとえば、町にとってAというアイディアが良いというひとと、Bというアイディアの方が良いというひとがいる。
わたしはAとB、どちらのアイディアの魅力も欠点も、それなりに理解できる。
でも、だからこそ困惑する。
「町の思いを発信するなら、AとBのアイディア、どちらを選べばいいのだろう?」と。
「Aを支持するひと、Bを支持するひと、どちらの思いも大切にしたいなら、わたしはどうやって言葉を紡げばいい?」と。
編集するひととして地域で暮らし始めたら、ますます裏方に徹することはできない。
「下川に住む誰かがこんなことを言っていたらしい」と、主語がぼやけることは少ない。地域のひとたちは「立花実咲はこう言っていたらしい」と、わたしの姿をはっきりとらえる。
それを、窮屈だと感じるひともいるだろう。
Aが良いと言えば、Bを支持するひとは目くじらをたてるだろうし、逆もまた然り。
「編集者としての意思よりも、地域での人付き合いを優先しよう」と、忖度を重ねて結局言いたいことが何なのか分からなくなるということも、きっとある。

地域で暮らす人々に意思があるように、わたしにも意思がある。
「どちらの思いも分かるけれど、どちらかを選べと言われても選びきれない」という、グレーな意思が。
編集者として本当に届けたいのは、AとBのどちらにも決めかねるわたしの戸惑いを、黙って見守ってくれる町の風土だ。
たいていは「AとB、君はどちらにつく?」と聞かれるだろう。
けれど、どちらに決めろとも言われない。AとBどちらでもないわたしのグレーな意思を、尊重してくれる。
「地域の魅力」という一言でくくられるコンテンツは、きれいな風景やおいしいごはん、満点の星空、すてきな人々……も、もちろん魅力的だけれどそればかりではない。
自分の意思を持ち、それらがつぶされずに尊重される風土があるかどうかが、なによりも地域の価値になる。
そうした風土をつむぎ出すのは「地域で暮らす編集者」だからこそ、できることなのかもしれない。