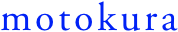「灯台もと暮らし」編集部のひとりであるぼくは、おもに写真の撮影やその編集を担当しています。じつは最近、稀にですが「写真がいいね」と褒めていただく機会があります。その一方で同じような構図の写真ばかり撮ってしまうこともあり、灯台もと暮らしの質を高め、チームの一員として貢献するためにも、写真で伝える技術を高めていきたいという思いがあります。
そこで、編集部員がこれからの暮らしを考える企画【ぼくらの学び】のなかで、「どうすれば思いが伝わる写真が撮れるのか?」という問いを、写真が上手な方にうかがいます。
今回ぼくが尋ねたのは、博報堂のコピーライターとして活躍する尾形真理子さん。「恋は奇跡。愛は意思。」といったLUMINEのコピーや、資生堂のキャッチコピーを手がける人物で、2015年からは博報堂が発刊する広報誌『広告』の編集長を務めました。

彼女は紙面構想中や取材・撮影ディレクションの最中、写真で伝えるためにどのような工夫を凝らし、どんな想いを込めてきたのでしょうか?
今あなたの手元にあるカメラで撮影する時にも活きる大切なこと、そしてレンズを通して世界を見るたのしさを学びます。
* * *
尾形 真理子(以下、尾形) 写真はお好きなんですか?
── ぼく、じつは大学で写真部に入っていました。写真が好きで仕事にも活かせるのでメディア業界に入ったんです。
尾形 そうなんですね。それはぜひ、企画としてはカメラマンの方にお話を聞きに行ったほうが(笑)。
── 昨年、尾形さんが登壇したIMA CONCEPT STOREのシリーズイベント「写真と雑誌の密なる関係」というイベントでお話をうかがって、どのように写真を使い、どう読者に伝えるのか、考えていらっしゃることがすごく勉強になって。共感するところや驚くところ、とにかく学びがたくさんありました。今回はあらためてお話をうかがいたいと思ったんです。

尾形 なるほど。『広告』は雑誌でもありますが博報堂の広報誌で、企業活動の広報を担う一プロジェクトです。私の本職はコピーライターで編集や撮影のプロではないので、今回の企画でレクチャーするには及ばないことがありますが、できるかぎりの内容をお話させていただきますね。
── ありがとうございます。尾形さんが『広告』を編まれてきたなかで大切にしてきた写真のことを、おうかがいさせてください。
「言語だけですべてが伝わるわけじゃない」という感覚
── そもそも尾形さんは写真を撮るんですか?
尾形 今はみんな撮った写真をFacebookとかInstagramに投稿したりしていると思うんですけど、私は日常生活で全然写真を撮らないんですよ。結婚式に行っても写真を撮らないくらい。
── そうなんですね!
尾形 ほぼ撮らないんですよ。
私の仕事は、アートディレクターと組んでコピーライターとして仕事をすることが前提です。その時に、「言語だけですべてが伝わるわけじゃない」という感覚はすごくありますね。言語で伝わる部分もある。けれどすべてのことが言葉に置き換えられるわけじゃない。それは私の職業観の前提としてあります。

── 『広告』をつくる上で、写真はどのような存在だったのでしょうか。
尾形 逆に写真も、写真だけですべてが伝わるわけじゃないはずなんですよね。もちろんレンズの先にあった時間の、ある部分は切り取られているけど。
言葉とヴィジュアルは訴求効果が高いから補完関係にあるべきだと思っているので、その写真の中に存在しない言葉を載せた時に世界が広がると考えています。
── 世界が広がるというのは?
尾形 言葉においても写真においても、空間を切り取っている誰かの視点が必ずあります。ひとつの視点で見せるよりも複数の視点で見せたほうが、輪郭線がはっきりしてきますよね。
言葉や写真、イラストもデザインもそう。そういうツールとそれぞれの視点で為人(ひととなり)を描いていきたいと思って『広告』をつくってきました。
── 写真は伝えるツールのひとつなんですね。
お会いして話を聞きながら、何をどう撮って誌面をつくるか考える
── ここからは実践している具体的なお話をうかがいたいです。尾形さんが撮影のディレクションをする時に大切にしていることはありますか?
尾形 ふつうの広告の仕事だと、何を撮るか最初に決めてから撮影に臨みますが、この雑誌はご協力いただく方にお会いしてお話を聞きながら、何をどう撮って誌面をつくるか考えています。
── 主に被写体の何を撮っていますか? 注目すべきポイントが知りたいです。
尾形 どこに着目をするかというのは、ご本人のお人柄が滲みでるところに着目して、ヒントを得て決めている感じです。だからお会いする前から「このひとは、こういうひとだろう」と決めつけないようにしようと思っているんですね。
── 『広告』を拝見していて、気になるところがあったんです。特集「70年と1歩」で掲載している将棋棋士の羽生善治(以下、羽生)さんの写真なんですけど……。
尾形 この写真ですね。

── ぼくだったら、この羽生さんの写真を誌面に選びづらいなぁと思っていて。このカットがバストアップなら使いたいですが、ほぼ頭部だけが写っていますよね。どうしてこのカットを選んだのでしょうか。
尾形 この写真、おっしゃるようにもともとバストアップで撮っているんです。でも、ここで羽生さんの印象として伝えたかったのは、羽生さんの頭の中ってどうなってるんだろう?っていうことで。
羽生さんは、普通のひとがちょっとびっくりすることを考えていらっしゃるんですよね。脳みそみたいなところにフォーカスしたいと思ったら、それはもう頭部を象徴的においたほうがいいんじゃないかと思って、この写真は、わざわざ上側の余白を画像編集して足しているんですよ。
── ほんとうですか(笑)。
尾形 デザイナーの子にも、「えぇ! そんなことするんですか」って言われて。そういうのもつくりながら考えています。
── なるほどなぁ……。でも頭部を象徴的に伝えたいのであれば、頭に寄って撮ったカットを載せる気がします。
尾形 けど、やっぱりここ(羽生さんの頭の上あたり)の空白が大事。彼の頭のなかで考えていることが、雲みたいにモクモクって出てくるイメージで。ここを大きく空けておくと、少しだけ頭のなかを覗いてる気分になるんです。
── なるほど……!
その企画やページで「何を伝えたいのか」。綺麗な写真が正しいわけではない
尾形 大切なことは、その写真で「なにを伝えたいのか」なんですよね。そこが明確じゃないと撮るべきものがわからないし、なんとなく「いい感じのもの」っていうふうにするしかない。そうなってしまうと相手の方に失礼なので、いつも何を伝えたいのかをはっきり持つようにしてきました。
── お話をうかがったその場で「こういうことを伝えたい」ということを、リアルタイムで決めていくのですね。
尾形 そうですね。そういう意味では話を聞きながら記事の編集をしていたと言ってもいいかもしれません。実際にインタビューをして写真を撮って、その現場でこういうふうにしようって思っていたイメージに合わせて、帰ってきてからカリカリ書くみたいな循環でしたね。
── 羽生さんを撮影した意図をうかがって、伝えたいことが大事だということがよくわかりました。ですが、これもすごく気になっている写真です。


── 特集「これからの母性は」のなかの「すごい女を育てた女」という企画で掲載された、蜷川宏子さんの写真です。下の写真ってよく見ると、被写体にしっかりピントが合っているわけではないですよね。

尾形 蜷川宏子さんの表情が豊かでお人柄が出ているから、これがいいなと選びました。
── ぼくみたいな初心者が抱いている「綺麗な写真が正しい」という写真の選び方とはまた違う視点だと感じます。
尾形 このページにおいて一番大切なことは、ピントがしっかり合うことでも、蜷川宏子さんがまっすぐ構えてちゃんと写っていることでもなくて。彼女の感性の豊かさみたいなもので誌面のシズル感をつくりたいなと。その感受性が娘の蜷川実花さんにも伝わっているところだと思います。
ピントがしっかり合っていることは、いわゆる正しいと言われていること。でもピントが合うことよりも大切なものがあれば、そっちを優先したいのが私の考えです。
── 繰り返しおっしゃっている「何を伝えたいのか」なんですね。
尾形 はい。大切なことって、変わるんです。だから、何をこの企画のキモとするか、核のつくり方によって大切なことが変わってくるのかなって思いますね。
たまたま『広告』を一緒にやっていたアートディレクターが自由な発想を持ったひとだったので、余計その色が強いっていうのはあるかもしれない。そういうADだから私は気が合ったところはあるんだろうけど(笑)。
「こうじゃなきゃいけない」みたいな論理や空気感をなるべく排除して、撮って伝えていくほうがおもしろいんじゃないかな。
“なぜか愛せる”、その要素に気付ける視点を持ちたい
── 媒体や企画で大切にしていることを伝えるための写真――大切なことは時として綺麗さじゃない――というのは、たしかに尾形さんが編集長として編んできた『広告』のすべての中で一貫していると思います。この編集方針の根底にあるものは、「なぜか愛せる人々」を伝えたいという想いなんじゃないかって、やっといま、感じています。
尾形 『広告』の通年テーマに「なぜか愛せる人々」を掲げたのは、理由は分からないけれど惹かれるひとや、その理由をたくさん見つけられたほうが、生きやすくなるんじゃないの?って思ったからです。そのために2年間、いろいろなひとの魅力に気づくきっかけになるようなコンテンツをつくってきました。
たとえば「このひとはかっこよくて、おしゃれで、背が高くて、女の子に親切で」って一見完璧な要素に、「ちょっとクサくて」みたいな側面が加わっても愛せるなら、もっと愛が深いものになるはずなんですね。相手の魅力を感じている部分が多いほうが、たぶんひとと関わり合う社会のなかでは生きていきやすい。そういうふうに、“なぜか愛せる”要素に気付ける視点を、私自身が持ちたいと思って、このテーマを立てました。
2年間、担当した8号分それぞれに「水色の自己主張」だったり「いたずら心」だったり、いろんな特集を立ててはいるんですけど、やりたいことって結局、毎号同じなんですよ。
多様性……、寛容な社会っていうのかな、こうだって決めつけないこと。極端に言えば伝えたいことは、もうそれしかないんです。なので編集部のみんなは、すっごいむずかしがっていましたね(笑)。
── むずかしがっていたというのは……?

尾形 最後の特集の「勝手な使命感」って、1号の「水色の自己主張」と、ものすごく近いコンセプトなんです。でも、それを「水色の自己主張」というフィルターを通した時の企画と、「勝手な使命感」という箱の中に入れた時の企画って、伝えたいことは限りなく近いんだけど、ちょっとずつお弁当箱の中身が変わってくるというか。
── 伝えたいことが一貫して根底にあることは、物事を伝えきるために大切だと思います。見習います……! さいごに、どうして尾形さんのテーマが多様性あるいは社会の寛容性だったのかおうかがいしたいです。

尾形 うーん。……こうじゃなきゃいけないとか、こうじゃないと許されないみたいなことって、放っておくとどんどん増えていきます。たぶん組織もそうだし、人間の暮らしにおいてもそう。ルールって、増えることはあってもなかなか減ることはない。逆に今まで存在したルールを捨てるって、結構勇気がいることですよね。でも気づけば、どんどんいろんなものに縛られてしまう。
それは誰かに縛られているというよりも、自分で自分を縛っていくようになるんですね。もちろんひとは歳を重ねていくにつれて、子どもや親、自分以外のひとのことを考えて動く責任や役割が増えていきます。
── そうですね。
尾形 でも私は、縛られていくと同時にどこかが自由になっていかないとバランスが取れなくなっていくんじゃないかなぁって思っていて。
愛せるものが増えるというのは、自分を自由にするひとつのポイントなのかな? そういうことが好きなんでしょうね。
── 「なぜか愛せる人々」というテーマの裏に隠れているのは、多様で寛容な社会だったんですね。
尾形 「なぜか愛せるひと」って、ある意味最強ですよね。なぜか愛せるひとがいるように、なぜか愛せないひともいるじゃないですか。なぜか愛せないひとって「なぜか」と言いながら、じつはね、いくつかの言葉で愛せない理由を説明できるはずなんですよ。言葉にしないだけで、愛せない理由はすごく見つけやすいし、規定しやすいんでしょうね。でもなんだか「このひとはこうだから好きじゃない」ということにフォーカスすると、本当に息苦しくなってしまう。
逆に、愛せる理由って言語化しきれないところがありますよね。そういう曖昧なものが、社会のなかで少しでも多いほうが楽しそうだなって思ったんです。
── 実際に会ってお話を聞いてから、被写体のどこか愛せるお人柄やポイントに焦点を合わせてシャッターを切る。尾形さんが『広告』をつくるうえで大切にされてきたことの意味がわかったような気がします。
尾形 写真の話ができたか不安です……(笑)。
── これまでぼくは誌面に掲載されてきた写真を見て、はっきりと「いいな」と思ってきました。綺麗な写真が上手で正しいと思い込んでいたんですが、この雑誌の中の、多様な写真のあり方に共感しているんだと思います。自分が撮影する時、そして撮影のディレクションをする時に、今回教えていただいたことを実践していこうと思います。ありがとうございました!
お話をうかがったひと
尾形 真理子(おがた まりこ)
博報堂クリエイティブディレクター。ルミネ「わたしらしくをあたらしく」、資生堂インテグレート「ラブリーに生きろ♥」など、多くのコピーで人々の心をつかむ。また、広告業務の他に小説、コラムや歌詞も手がける。2015年より2年間、博報堂の発行する季刊誌『広告』の編集長も兼任。
この雑誌のこと
『広告』(こうこく)
1948年創刊。博報堂の社員が中心となって編集制作を担当している。397号~404号の編集長として尾形真理子さんが就任し、「なぜか愛せる人々」をテーマに展開している。公式サイトはこちら。
(文/タクロコマ)