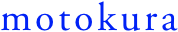「私はアートで救われるのか」。
「灯台もと暮らし」編集部が、自身のこれからの暮らしを考えるために、理想の暮らし方の先輩や知識人に疑問に思っていることを学びにいく特集【ぼくらの学び】のなかで、私(編集部・立花)が掲げた問いはこれでした。
なぜ芸術なのかというと、少し長くなります。私自身が芸術、とりわけパフォーミングアーツ(ダンス、演劇、音楽劇など)を観るのが好きで、その世界とどうにかして関わっていたいという思いを、この数年ずっと持ち続けていたからです。
“なぜ”救われたいのか、そして、“何から”救われたいのか。
“救い”というのは、「私は何者なのか」という不安や焦燥感、そして「何を言ってもどうにもならない」という社会のぼんやりとした諦めと閉塞感から脱する手段を、私がアートに対して託しているからだと気づいたことで導き出た言葉でした。とても抽象的で漠然とした問いかけではありますが、表現者でもアートの取り組みに携わっているわけでもない、一般人の私なりにアートと向き合う方法を探りたいと思ったのです。
第一回目は、NPO法人芸術公社代表理事の相馬千秋さんです。「フェスティバル/トーキョー」(以下、F/T)という豊島区を中心としたパフォーミングアーツの大規模な祭典の初代プログラムディレクターであり、私がずっとずっとお会いしたいと思っていた方でした。というのも、相馬さんを知ったきっかけは、2010年のフェスティバルトーキョーで、当時18歳の私がボランティアスタッフとして参加し、相馬さんのお話やフェスティバル内のプログラム作品と、イベントそのものの規模に、大きな衝撃と感銘を受けたからです。
遠巻きに「いつかお会いしたい」と思い続けた6年間を経て、いざぶつけてみた「私は芸術で救われるのか」という問い。果たして相馬さんの答えとは。
大人は私たちの問いには答えてくれない
── まさか相馬さんに取材をご快諾していただけるとは思っていなかったので、うれしいです。よろしくお願いいたします。じつはお伺いしたいことがたくさんあって……(メモを見る)。
相馬千秋(以下、相馬) よろしくお願いします。いくつか先に、私から質問をしてもいいですか?
── はい。

相馬 立花さんは、なぜ救われたいと思う? そして、何から救われたい?
── 私が漠然と感じている「何者かにならなければならない」という焦燥感や不安から救われたい、と思っています。同時に、アートはそういう“自分は何者か”という疑問や言葉にできない不安を表現しているものなのではないか、という仮説を、私は持っています。もしアートにそういう作用があるならば、私と同じような感覚を持つひとが、表現者や鑑賞する側になることで、不安感から解き放たれるのではないかと感じたからです。すごく広義で、抽象的な話になってしまい恐縮なのですが……。
相馬 なるほど、分かりました。
いま立花さんが話してくれたような、「何かをしなくちゃいけない」とか「何者かにならねばならない」という意識だとか、世界の中で自分を相対化して感じたり考えたりするようになったのは、じつは近代以降のことなんですね。
「自分は何者か」ということを厳密に考えようとすると、両親やその親、そのまた親まで辿っていくと祖先や類人猿に行き着きます。その更に先を考えれば我々は海から来た微生物で……と遡っていくことはできます。けれども「自分は何者か」という疑問に対する、明確な答えはないんですね。
── はい。
相馬 私も昔、そんなふうな疑問を抱いていた頃があります。小学校の卒業文集に、私という存在の小ささを感じて悩んでいるというようなことを書いていました。
私が暮らす日本は地球規模で見たら小さい島国で、地球でさえ小さな惑星だし、地球がある太陽系も銀河系のなかで見たら星屑くらいの存在なんだ、と。時間に関しても「11年間生きてきて、それなりにいろいろあったけど、私が生きているこの時間は人類の歴史にくらべたらなんて短いんだろう」と感じました。小学校6年生くらいになると、自分という存在がどれくらい小さいかを知る視点を得るわけです。
それから最近、漫画家のいがらしみきおさんとお話させていただく機会がありました。『ぼのぼの』が有名な方ですが、ほかの作品でもとても哲学的な漫画を描かれている方です。お会いした時、いがらしさんが「子どもの頃に感じた『なぜ自分がここにいるのか』という疑問は、誰かがいずれ答えてくれるだろうと思っていた。でも、誰も答えてくれなかった。自分が表現をするのは、そのことに対するルサンチマン(*1)なんだ」とおっしゃったんですね。
(*1)ルサンチマン:怨恨、復讐を意味する語(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典参照)
── はい。
相馬 誰しもが持つそういう感覚は成熟する前まで持ちうるものですが、大人になるにつれてみんな忘れていく。忘れていける。あるいは別の形で消化できるのだけれど、いがらしさんみたいに「自分は何者か」という疑問を内在させて創作の原動力にしている――ある種、せざるをえないのかもしれません――そういう方々がいるということに、私はとても救われた気持ちがしたんですね。
── 何故ですか。
相馬 表現をすることで、自分の違和感をきれいに解消することはできないまでも、違和感と格闘することと、そしてその違和感と向き合う手段には成りうると感じたからです。その表現したものが、他者に向けられた瞬間に、アートになっていくんじゃないかなと思います。
── 表現しているひとは、戦っているのですね。
相馬 何かに対する具体的な怒りや恨みを持っているというよりは、根源的な問について一生かけて考えていきたいということですよね。そしてそれは、アートだけではなくて、宗教や科学も違う方法論の中で取り組んでいますから、アートだけを特権化する必要はないと、私は思います。
── 言葉にならない不安や悶々とした思いをぶつけるために、ひとは表現をしたり、創作をしたり、もしくはそれを享受したいと思うのでしょうか。
相馬 そうですね。表現と一言に言っても、いろいろあって。個人が誰にも頼まれずともやらずにはいられないものもあれば、アートフェスなどで自治体からオーダーされてつくられるものもある。私は基本的にどちらもあってよいと思っているんですれど、アーティストって、子どもの頃に世界のいろいろなものを見聞きしたときに獲得する感動とか違和感を、ずっと持ち続けられるひとたちなんじゃないかと思っていて。自分の子どもを見ていて、そう感じるんです。
── どうしてですか。
相馬 3歳の子どもがいるんですが、子どもを見ていると、人間は表現するものだということをとても実感するんです。ある程度五感が発達してくると、1歳になる前くらいから、表現の欲求みたいなものがすごくあって。あっという間に歌うようになるし、あっという間に何かを描くようになるし、あっという間に踊るようになる。そしてあっという間に真似事をするようになる。お母さんの役や犬の役を演じるようになるんです。アートが持っている基本的な要素を、子どもは教えなくてもどんどん体得していく。これはアートの教育を受けるとか受けないとか、リテラシーがあるとかないという問題以前に、すべての子どもは表現者なんだなって。出産するまではそんなの嘘だろって思っていたんですけれど(笑)、本当にそうだったんですね。

相馬 人間が生きるために持っている根源的な表現する力みたいなものこそが、もっとも重要だなと感じますよ。大人になるということは、むしろそれをひたすら忘れていく過程なんじゃないかなって。
── 先ほどの相馬さんの卒業文集や、「私は何者か」という疑問と、ずっと対峙し続けるという話にも通じますね。
相馬 世界を認識していくプロセスの中で「自分はなんて小さいんだろう」という相対的な視点を持つとか、知らなかったことを知るとか、いろんな驚きや感動を獲得するたび、子どもはそれらと全身全霊で向き合っていて、同時に表現を生み出しているんだって。大人になるということは、そうした一つひとつの発見や衝撃に、慣れていくプロセスなのかもしれません。
宗教は「世界の成り立ち」を示してくれる。アートは?
── 私が、誰しもが向き合ってきた違和感や疑問を、未だに持ち続けて悶々としているのは、未熟だからなのでしょうか……。
相馬 これは極論ですが、もし立花さんが本当に救われたいのであれば、宗教に入信することだってできるわけです(笑)。
── たしかに、そうですね。
相馬 たとえば「私はどこから来たのか」とか「死んだらどこへ行くのか」といった疑問は、宗教的価値観が確固たるものとしてあれば、解決できるんですね。人間は死んだら天国へ行けるとか、また別のものに生まれ変われるとか答えをくれるから、私たちもある程度納得できるわけです。
たとえば教会とか神社仏閣には、様々な物語やパフォーマンス、絵画が存在します。神社には何百年も前に奉納された絵画が納められていたり、神楽があったり、教会であれば賛美歌や宗教画がある。そして聖書や教典には、世界がどうつくられているのかという物語が記されていている。それぞれ個別の宗教は、いろいろな表現物を媒介にして、この世界がどうなっているのかを示してくれています。でも、今は単一の宗教を信じることができない時代にいる。そして立花さんが、そういう視点を持ってしまっている。すると、一体何を信じたらいいのかという気持ちになるのは、自然なことだと思います。
── 宗教となると、なんとなく良くも悪くも排他的な考え方になってしまう気がして。
相馬 一つの神様や宗教を信じきれないというのは、苦しいけれど、豊かなことでもあって。単一とか単数ではないものの見方や、現実の把握の仕方を提示するために、アートは有効だと思います。

相馬 よく「アートで社会は変わるか」というテーマで質問をされることもありますが、アートはそもそも社会を直接的に変えるためのものではないんですね。社会を変えるといっても、仕組みを変えたり行動様式を変えたり、社会の“何を”変えるのかによって役割がありますし、そういう意味でアートは、人間が社会を把握する時に単純に言語化できない問題を表現してきた歴史があります。と同時に、社会の空気のようなものをいち早く察知して予言する力だとか、あるいは起こってしまった歴史を反省したり、歴史からこぼれてしまったものをすくいあげたりする機能がある。アートが革命的に社会を変えました、ということは、いちアート作品や、いちアーティストが起こせるとは思いづらいけれども、アートを通してものの見方を複数化したり抽象化したりすることは、確実にできると思っています。
社会が変われば表現方法も変わる
── 余談になるのですが、私は今年の夏休みに初めて富山県の利賀村(*2)に行きました。あんな山奥の村に、世界中から舞台を観にあんなにたくさんのひとが集まっているという事実に、とても感動しました。同時に、演出家の鈴木忠志さんが「僕らがやっていることは世直しだ」(*3)とおっしゃっていたことがとても印象的だったんです。
(*2)富山県の利賀村:富山県東砺波郡利賀村のこと。1976年に、演出家である鈴木正氏が東京から富山県利賀村に拠点を移し、SCOT(Suzuki Company of Toga)として活動している
(*3)参考:『ゲンロン1 現代日本の批評』
相馬 私も今年初めて、利賀村に行きました。向こうで鈴木さんにインタビューを申し込んで、2時間くらいお話させていただいたんですけれど、その時に「自分たちの時代において、演劇は社会を変革するために有効な手段だと思ったから選んだ」とおっしゃっていました。今、演劇に関わる若いひとというのは、演劇が好きだからという、ある種趣味が拡大したような動機で始めるひとが多いけれど、社会と自分の関係性が反映されていないんじゃないか、と。
── はい。

相馬 鈴木さんたちが利賀村に移ったり、寺山修司が一世を風靡したりした60年代はアングラ(*4)の時代で、革命を志す若い学生が社会の原動力となっていたり、高度経済成長の前だったり、今とはぜんぜん雰囲気が違いました。ですから、社会的な芸術である演劇も、時代によって有り様を変えるし、私は変わっていいと思っています。強靭な肉体を駆使するスズキ・メソッド(*5)も、当時の社会情勢を考えれば必然性のある表現だった。けれど今の時代にコミットしようと思ったら、別の新たな表現方法があっていい。俳優の身体ではなくて、観客の身体を問題にするような演劇ですとか、それこそF/Tで取り扱ったような、観客参加型のものとかツアー形式のものとかですね。
誰かが舞台の上で激しく演じているのを見るだけではなく、自分が自分と向き合うために主体的に参加するアートも、あっていい。固定的に「演劇はこうあるべき!」とか、「劇場はこうあるべき」と考え続けたところで、アートの世界における表現の革命は起きないと思います。
(*4)アングラ:アンダーグラウンドの略。商業性を無視し、独自の主張をする前衛的で実験的な芸術。または、その作品。1960年代に米国で発生して、日本にも普及した(デジタル大辞泉参照)
(*5)スズキ・メソッド:鈴木忠志氏が編み出した、スズキ・トレーニング・メソッドと呼ばれる俳優訓練法のこと

圧倒的に良質な作品を浴びる機会が、まったく足りていない
── 私がアートに救いを求めるのは、画一的なものの見方には嫌悪感があって、アート作品で特にパフォーミングアーツが、その感覚を形にしてくれるから「私がこう思うのは間違っていないんだ」と認識できるからなのかもしれません。だからこそ、私のような漠然とした不安感を感じているひとが、アートを受け取れる場がもっとあったらいいなと思いますし、もっと観に行くひとが増えたらいいなと思います。かつての私がF/Tで衝撃を受けたように。
相馬 アートを受け取る側というのは、日本では未だにマイノリティです。たとえばF/Tの1ヶ月の動員数は、野球の一試合のドームの来場数にも満たなかったんです。
── そうなんですね……。なんとなく、地域の芸術祭やアートイベントが増えているので、アートに興味関心のあるひとは増えているのかなという印象でした。

相馬 もちろん、動員数で言えば伸びているところもあります。でも、これだけイベントが増えているのは、国の政策が絡んでいるからなんです。本当の意味で良質な舞台を圧倒的に浴びる機会というのは、まだまだまったく足りていない。F/Tでは、私がディレクターを務めていた頃は、1回3億円規模のイベントを連続して6回行いましたし、今でも継続されていますが、ああいう規模のパフォーミングアーツのイベントは未だにF/Tくらいしかありません。
先の野球の例で言うと、野球場という場所があって、それをテレビやラジオ、新聞で中継したり取り上げたりしていますよね。すると関心のある層が厚くなって、情報の量も質も上がっていきます。
かたやアートとなると、距離やお金の問題で観に行けないひとが多いから、メディアで取り上げてもらえない。でも本当は逆で、観に行けないひとが多いからこそ、どんどん載せて知ってもらうべきなんです。特にパフォーミングアーツとなると、観客数が増えないのは他のエンターテイメントに比べておもしろくないからだ、難しいものが多いからだと言われます。でも、問題はそれだけではないはずなんです。
生の舞台に触れる機会を、もっと増やさなければならないと感じるし、そのためにどうするべきかは、ずっと考えていることでもあります。

── 触れる場を増やすために、相馬さんご自身が取り組んでいることは、何かありますか。
相馬 私は「劇場」ということをもう一度考え直したいと思っています。理由はいくつかあるんですが、ひとつは単純に劇場をつくりたいという気持ちがあります。お客さんを含めた身体的な経験を共有できる時間や空間というのは、やっぱり圧倒的に強いから。
その体験の価値を地域振興やツーリズムと接続したのは北川フラムさん(*6)ですが、私は都市の中で、身体的な経験をしっかりと受け取れる場をつくりたい。フェスティバルのような非日常的なものとしてではなく、もっと日常に寄り添いながら身体的な強度を感じることのできる時間や場所をどうやったら組織できるのかということに興味があります。
(*6)北川フラム:アートディレクター。地域づくりの実践として、「ファーレ立川アート計画」(1994/日本都市計画学会計画設計賞他受賞)、2000年にスタートした「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(第7回オーライ!ニッポン大賞グランプリ〔内閣総理大臣賞〕他受賞)、「水都大阪」(2009)、「にいがた水と土の芸術祭2009」「瀬戸内国際芸術祭2010、2013」(海洋立国推進功労者表彰受賞)等(ART FRONT GALLERYより引用)
── あえて都市でやる、東京でやるということでしょうか。
相馬 都市での生活を手放せない、手放したくないひとというのはたくさんいますよね。それは会いたいひとがいるからとか、仕事があるからとか、いろいろな理由があると思いますが、大都市圏で暮らすひとが未だに圧倒的に多いというのは隠せないリアリティです。ですから都市の生活を全否定して山にこもろう、という単純な話には、私はできないと思っています。
私も今年の夏に東北や各地を回っていて、山や海といった身体が活性化する場所にいて久々に東京に戻ってくると、暑いしひとも多いし、満員電車イヤだなーと感じたりもしました(笑)。今の都市は、そういう身体が活性化しない場所になってしまっているんですね。あらゆる規制によって管理されて均質化されてしまっている。でもその都市の空間を、もう一度蘇らせたいと考えています。
── 都市が、身体が活性化する場所として蘇るために、具体的にどんなことをしていきたいと考えていらっしゃいますか。
相馬 じつは今年度の後半に向けて、劇場をつくるプロジェクトをやろうと思っていて。具体的な場所を持っているわけではなく複数の場所を使いつつ、都市をメタ劇場みたいなものに捉えて、いくつかの作品を紹介しようと思っています。既存の劇場という固定的なハコとシステムはありつつも、それをどうやって概念的にも空間的にも拡張できるかということにチャレンジしたいんです。
── 代々木公園や上野公園で同時多発的に作品をつくったり観たりできる、というようなイメージでしょうか。
相馬 そうですね。都市で暮らしながら、身体が覚醒するような経験を、どうしたら我々は持ち得るんだろうかと考えています。もしかしたら、その経験のうちに、たまに地方に行くというプロセスも含まれるかもしれない。地方か都市かという二項対立は、私はもはやすでにとても古いなと思っていて、どちらも行き来していいし、するしかないと思っています。その現代のリアリティをベースに、都市の中でできる、今までにはない形の“劇場”がどんなものなのか実験してみたいなと思っています。
取材を終えて
相馬さんのお話を伺いながら、アートに携わる当事者でない自分が、今までどれだけ頭でっかちにアートというものを捉えてきたのかということと、アートに頼りきっている自身のある種の傲慢さを思い知り、正直とても恥ずかしくなりました。同時に、アートで誰かを救いたい、誰かを救うアートとは何なのか考えたいという気持ちも湧いてきました。ずっと現場を引っ張ってきた相馬さんの切実な思いや言葉が、アートに少しでも興味のある誰かに届きますように、と願っています。(撮影協力:立教大学 池袋キャンパス)
お話をうかがったひと
相馬 千秋(そうま ちあき)
アートプロデューサー。国際舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー」初代プログラム・ディレクター(F/T09春〜F/T13)、横浜の舞台芸術創造拠点「急な坂スタジオ」初代ディレクター(2006-10年)、文化庁文化審議会文化政策部会委員(2012-15年)等を歴任。2012年よりr:ead(レジデンス・東アジア・ダイアローグ)を創設、アジアにおけるコミュニケーション・プラットフォーム作りに着手。2014年仲間とともにNPO法人芸術公社を設立し代表理事に就任、法人の経営や各種事業のディレクション全般を行う。また国内外で多数のプロジェクトのプロデュースやキュレーションを行うほか、アジア各地で審査員、理事、講師等を多数務める。2015年フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章。2016年より立教大学現代心理学部映像身体学科特任准教授。