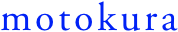2016年にはじまった、「ぼくらの学び」という特集。
わたしは「アートは誰かを救えるか」というテーマで、いろいろな方々に話をうかがってきました。



焦がれるように皆さんの話に耳をすまし、自分にとって、誰かにとって、アートはどんなものなのだろうと、考えつづけていたある日。
お世話になっている方が「アーティストは課題解決はできないけれど、問いを立てる天才だ」とおっしゃっていたのを聞いて、はたと、気づきました。
「自分の内面の切実な問いに向き合っているひとに、猛烈に惹かれる。そしてその向き合い方が芸術作品に反映されていると、より一層惹かれる」ということに。
だから今度は、アートやアートに携わる方々に、こんなことを、うかがいたいと思います。
「今、あなたが掲げる、もしくはかかえている“問い”は何ですか」。
またしても、モラトリアム全開な特集のはじまりです。
けれど、自分にとっての切実な問いが、アートを媒介して、誰かの思いと重なると信じています。
わたしが、アートを通じて自分の“問い”を見つけたように。

「今、あなたが掲げる、もしくはかかえている“問い”は何ですか」というテーマで、最初に取材をしたのは、ここ数年でとりわけ注目されている劇団「範宙遊泳(はんちゅうゆうえい)」の、山本卓卓さんです。
山本さんの作品は、役者の台詞や効果音が舞台上にプロジェクションマッピングのように投影されたり、光や音が役者の動きとシンクロしたりコミュニケーションをとっているように見えたりする演出が、多く使われています。

『午前2時コーヒーカップサラダボウルユートピア-THIS WILL ONLY TAKE SEVERAL MINUTES-』
2017年 東京公演 撮影:鈴木竜一朗


国際舞台芸術祭である「フェスティバル・トーキョー」での映画「Changes」上映(11月14日に終了)に加え、舞台「#禁じられたた遊び」(11月23日〜28日)の上演を控えていた山本さん。
新作を2つ、同時並行で制作しているという多忙のさなか、ご快諾いただいた今回の取材。よく打ち合わせなどで使っていらっしゃるという都内のカフェで、お話をうかがいました。
1人を撮り続ける映画と、16人の背景に迫る舞台作品
── 「どんな問いを立てているか」というテーマでお話をうかがえればと思います。「問い」は、いま山本さんがつくっている作品に込めた問いでもいいですし、一貫している問いでもいいのですが。よろしくお願いいたします。
山本卓卓(以下、山本) はい、分かりました。お願いします。

山本 いま(2018年10月時点)、映画と舞台を並行してつくっています。舞台は「#禁じられたた遊び」という作品名で、16人が出演しますが、外国にルーツを持つ人や日本語以外の言語を喋ることのできる人を求めて、オーディションをしました。
外国籍の方もいれば、日本で生まれ育ち国籍は日本だけれど、外国に親族を持つ方。外国語が話せる方と話せない方。非常に多様な座組みになりました。
── 劇中で使われる言語は、日本語以外も登場するのでしょうか。
山本 はい。中国語、韓国語、英語、そのほかにも。

山本 映画「Changes」は、もう撮り終えていていま編集作業中なんですが……なんでこういう作品になったんだろうって、自分でも疑問なんです(笑)。
── それはいい意味で疑問、ということですか……?
山本 もちろん、いい意味で。結局こういうテーマに行き着くんだなって自覚したというか。
映画は田中美希恵という、一人の女優しか登場しないんです。彼女は、最近僕の劇団を退団して、彼女のドキュメンタリーとして撮っています。
劇団を辞めるということは、仕事とか生活のいろいろとか理由はあるとは思うけど、そこに居られないっていうのは、なんらかの価値観、どこかの部分が擦り合わなかったからだろうなって思う。
僕は、その分かり合えなかった部分に何があるのかを、知りたくなったんですよね。だから撮りました。


山本 こういうすれ違いは、僕の個人的な体験で終わらせていいものじゃないと思うんです。たぶん誰でも、会社の上司とか、恋人同士とか、うまくいかないことってあると思う。けど、そこに対してじっくり考える時間もない。
じゃあこの(すれ違ってしまう状態の)正体はなんだろうって考えたくなったんです。その後の人生を、よりよく生きていくための実験ですね。
分かり合えなかった一つの事例として、提示したいという気持ちもあります。
「めんどくさいもの」だから価値がある
山本 舞台「#禁じられたた遊び」については、もう一つ新しい挑戦をしていて。
今回は国際共同作品を日本でつくるとするなら、自分ならどんなものをつくりたいかを考えたときに、「招き入れる」形にしたいと思ったんですよね。
── お客さんを招き入れる、ということですか。
山本 そう。もともと演劇は旅芸人的に、各地を回って公演するという歴史はあります。僕も、東南アジアやインドへ移動して作品をつくってきました。でも異国での上演は、残念ながらコスト面でどうしても小規模な形式でやるしかなくて、大人数の作品は難しい現実があります。
だから今度はこちらが出向くのではなくて、お客さんに来てもらおうと思って。
お客さんがより来やすくなるように、一都六県外から来られる方は安くなる遠方割や、天井桟敷という割引チケットも用意してみました。
── どうして招き入れることを重視しようと思ったんですか?
山本 「わざわざ行く」、そのイベント性の大事さと強さを、ちゃんと感じてほしいなって思ったんです。
いまってなんか……シンプルブームというか。単純化することにみんなが慣れていて、そういうものを享受してばかりですよね。
「演劇ってめんどくさいじゃん、劇場に行かなきゃいけないしさ」ということではなくて、行くことが大事。行くことが価値だってことに変換していきたいんです。
「YouTubeでいいじゃん」じゃなくて、むしろ演劇の良さは「来なきゃいけない」というところにある。「来ないと見れません」っていう価値を、今回は特にちゃんと伝えたいなって思っています。
見たいものだけ見ていられるけど、世界はもっと複雑だ
── 先ほど、映画をつくるなかで「結局このテーマに戻ってくる」とおっしゃっていましたが、映画と舞台に込めた“問い”は共通しているんですか? どんなものなのか、知りたいです。
山本 うーん、なんだろ……。
人間って、ぜんぜん単純じゃなくて、どうしたって重層的だし多面的だし、多様。でも、さっき言ったみたいに、今ってシンプルブームだから。即席でつくれるものが好まれるし、儲かるし。
あと、見たいものしか見ないようになっていますよね。ぜんぶ。見たいものしか見なくていい。
でも、不快なものも、この世の中にはある。
見たくないものとか本当は誰しも目を背けたいものを、アートは表現できるんじゃないかって。僕はそういう、演劇が持つ、ジャーナリズム性を信じているから。
── 映画「Changes」だと、「なぜ分かり合えなかったのか」を探る映画だというお話でしたよね。本当は「分かるひとだけ分かればいい。分かり合えないなら、それっきりサヨナラ」って突き放しちゃう方が楽なのに。
山本 そうですね。舞台も16人も多様なバックグラウンドを持つ俳優が出るので、16通りの人生や考え方があります。
基本的に、考え方が合わないひととか、気が合わないひととは一緒にいたくないじゃないですか。でも、なんていうんでしょうね、それって、当たり前だから。その前提から、何かできると思っていて。

山本 演劇って本来、メディアなんですよね。シェイクスピアだって、当時一番ホットな話題をテーマにしているはずですし。時代の記録として、日常を演劇作品に取り入れていいはずなんです。
実際に僕は、コンビニとか街中で外国人を見かけるし、それが普通になっていっている。だったら、その日常を演劇が取り上げないわけにはいかないと思うんです。当たり前のことを当たり前に表現していくという大事さがあるんじゃないかなという気がしていて。

山本 ここから日本人の価値観ってもっと変わっていくんじゃないかって思います。今は、その転換点みたいなところなんじゃないかって。
これから先、日本のひとたちが差別的になってほしくないなって思うし、お互いに対しての無理解、無関心のせいで、引き裂かれてしまうようなひとたちをつくりたくないなって。
だから、考えも国籍も言語も違うひとたち同士が、同じ舞台上に存在していて、その存在を咎めない──そういう世界を表したいなと思っています。
ずいぶん前からマスメディアに対する怒りみたいなものがありました
── 演劇は、日常を多面的に見るためのメディアなんですね。
山本 そうですね。
……僕、昔からマスメディアへの怒りみたいなものが、ずっと、あるんですよね。作品の中で伝えたいことが、マスメディアへの怒りだと思うことが、結構あって。
── 怒り、ですか。
山本 マス向けのニュースは、だいたいいつも加害者と被害者の話で終わりです。受け取る側も「へえ、そんなことがあったんだ、大変だね」っていう感想で、おしまい。
加害者と被害者がいたとしたら、例えば加害者の家族は、ブラックボックスに入れられてしまう。僕が一番知らなくちゃいけないんじゃないかと思うのは、加害者の家族の感情なんです。
被害者の家族は、起きたことに触れてほしくないひともいるだろうから、そこは社会が守ってあげていいと思うんですけど、加害者の家族って悪者として一括りにされて終わり。でも本当は、そうじゃないはずで。
なんていうんだろう、マスメディアは、そういうひとにやさしくない構図になっているように感じるんですよね。「おもしろいから」という暴力性につぶされているというか。
「こういう風に演出した方がおもしろい」っていう理由だけで、周辺にいるひとを切り捨てる暴力性に、僕はずっと憤っているんだと思います。
── その怒りは、いつから抱えているものなんですか?
山本 わりと昔からですね。

山本 ……なんか、分からないですけど、すごく覚えている記憶があって。
僕が幼い頃に、僕の母親が、自動車事故の加害者みたいになってしまったことがあったんですよ。2人乗りの自転車が飛び出して、そこに当たって自転車に乗っていた2人が入院しちゃったことがあって。
で、ある日、僕が友達と喧嘩したんですよね。僕、そのとき友達に石投げちゃったんですよ。見たら、友達の額から血が出ていて。
その帰り道、「友達が、卓にこんなことされたってチクれば親に電話がかかってくるだろうし、自分は怒られる」って憂鬱で。すっごい嫌だなって思いながら家に帰ったら、ガレージで母が泣いていたんですよね。見たら、車がペコってへこんでいて。「今日、事故があったのよ」って言うんです。
── あ、同じ日に起きたんですか?
山本 同じタイミングで。僕は友達に石を投げた加害者で、しかも母も加害者になってしまった。結局、友達に石を投げて怪我をさせてしまったことは、その日は母親に言えませんでした。布団でずっとうじうじしていた思い出が、すごく強く残っているんですよ。
── それは確かに強烈な記憶ですね……。
山本 もし、この事故をニュースにするなら、僕の母は看護師だったので「40代の看護師が、少年2人に追突しました」っていう報じられ方をすると思います。場合によっては、母を責めるような内容も出るかもしれない。でも考えてみれば、2人乗りをしていた非もある。どちらかを完全な悪者にすることは、できないはずなんです。
ところが、ニュースは分かりやすく切り取る。しかも読者に対して「あなたたちなりにこの事件について考えてみて」とは言わない。パッケージングしちゃうんです。「これはこういうものでした」って。
それ以上、考えなくていいように。その方が売れるから。
でも僕は、語られなかった、切り捨てられてしまったひとたちのことも、考え続けたいんですよね。

言葉は無力。それでも。
── 山本さんが、一言でくくりきれない事柄に常に目を凝らしている理由が、わかった気がします。
山本 本当は、いろんな出来事は、なんとも言えないほど複雑なんです。でも、スッキリしたいから。
── 伝えたいことが複雑で、入り組んでいて、なかなか表現できないとき、言葉で伝える限界みたいなものは感じませんか。
山本 「言葉は無力だ」問題ですね。
── そうですね。
山本 「言葉は無力だ」問題は、必ずぶち当たりますよ。ぶち当たりますけど、いろんなことうじうじ言って、言葉に収まり切らないほうが、リアルというか、収まり切らなくていいと思います。
僕、写真も好きなんですけど、ぜんぶ見えちゃう写真って、つまらなくないですか。どうですか?(撮影している小松崎に向かって)
── そうですね。おもしろくないと思います。(小松崎)
山本 ちょっと見えない、何かが欠けている、ピンぼけしている、っていう方が、受け取る側が見ようとする。フレームの外側、写真に写ってない部分を「なんだろう」って想像する。
演劇も、わりとそれで。言葉で伝えすぎてしまうと、伝えたいことも伝わらなかったりする。
なんか見えない、なんかわかんない、こっちがピントを調節しないといけないことの方が、おもしろいし、本当のことなんじゃないかって思うんです。
結局たどりつくのは、人間の生活、人間の営み。人間の……滑稽さとか、どうしようもなさ。
なんでこんなにときめいたりイライラさせられたり、傷つけられたりしなくちゃいけないんだろうって思うんですけど。
僕のなかでは、演劇でも映画でも、作品の表現方法は変わったとしても根っこで流れているものは、同じだなと思います。
取材・文/立花実咲
写真/小松崎拓郎
お話をうかがったひと

山本 卓卓(やまもと すぐる)
範宙遊泳主宰。劇作家・演出家。1987年山梨県生まれ。
幼少期から吸収した映画・文学・音楽・美術などを芸術的素養に、加速度的に倫理観が変貌する、現代情報社会をビビッドに反映した劇世界を構築する。近年は、マレーシア、タイ、インド、中国、アメリカ、シンガポールで公演や国際共同制作なども行ない、活動の場を海外にも広げている。『幼女X』でBangkok Theatre Festival 2014 最優秀脚本賞と最優秀作品賞を受賞。2015年度より公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェロー。2016年度より急な坂スタジオサポートアーティスト。2017年度よりACYクリエティブチルドレンフェロー。ACC2018グランティアーティストとして、2019年に半年間のNY滞在を控えている。
新作公演『#禁じられたた遊び』は、11月23日(金・祝)〜28日(水)まで、吉祥寺シアターにて上演。