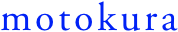「“アートでわたしは救われるか”なんて、そんなことを言ってくれる方が、まだいたんだと思いました」。
ロンドンの曇り空から時折気まぐれに覗く日差しを浴びながら、演劇研究者・ジャーナリストの岩城京子さんは、わたしにそうおっしゃいました。

「アートでわたしは救われるか」という問いと、そこから派生した「わたしはアートで誰かを救えるか」という2つのテーマの発端は、2016年の5月に遡ります。
当時わたしは、イギリスのマンチェスターとブライトンという2つの都市で同時開催される「SICK! Festival」というパフォーミングアーツに関する記事を読み、衝撃を受けました。
記事内に登場するのは「SICK! Festival」の芸術監督であるヘレン・メドランドさんと同イベントの企画開発ディレクターである、ティム・ハリソンさんの二人。そして聞き手と執筆は、岩城さんによるものでした。
それまで、舞台芸術が好きでも関わり方を明確に定められなかったわたしは「このフェスティバルには、自分にできることとアートの接点を見出すヒントがある」と直感し、2017年3月にイギリスはマンチェスターへ飛び、観客として「SICK! Festival」に参加してきました。
また「SICK! Festival」を知るきっかけになったインタビュー記事の書き手である、岩城さんご本人にもロンドンでお目にかかれることに。2017年3月時点で教鞭を取られている、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジの近くで、お話をうかがいました。


岩城京子(以下、岩城) こうしてロンドンまで(私の)取材に来られる方は、珍しいですよ。
── 「パフォーミングアーツネットワークジャパン」のサイトで岩城さんが執筆された「SICK! Festival」のインタビューを拝見し、これは観に行かなくちゃと思って。そして書き手である岩城さんにも、イギリスに来たからにはどうしてもお会いしたかったので、取材を申し込ませていただきました。
岩城 読んでいただいて、ありがとうございます。
── 「ぼくらの学び」という特集枠では、半年ほどかけて「アートで私は救われるか」という問いを掲げ、考えてきたのですが、この「SICK! Festival」が精神的な病を抱えた人々をアート(演劇やダンスなどのパフォーミングアーツ)で救っている事例なんじゃないかと直感したからなのですが−−。
岩城 「アートで私は救われるか」と聞かれたら、救われると、私は思いますね。私は日々救われていますよ。
── ……そうなんですね。
岩城 生きていると「どうしてだろう」と疑問を持ったり、違和感を覚えたりすることにたくさん直面します。でも、それを一つひとつ根本から疑って考えていると「あなたはおかしい」と言われたり、マイノリティだと一掃されてしまったりします。日本は特に、その傾向が強いと感じますし「違和感を持ってしまった自分が悪いんだ、呑み込めない私がいけないんだ」と自分を責め始めてしまう。
でも、アートはその違和感や、おかしいと言われるような考えを「おもしろいね」と肯定してくれる。もちろんアートが必要ないひともいますが、身近なものに疑問を持つことで生じるおもしろさって、絶対あると思っていて。
自分の生き方に対して、肯定感を持てないひとを救えるのがアートだと思いますね。
── うう……もうそれを伺えただけで、来て良かったと思いました。
岩城 依頼書をいただいた時、「アートで私は救われるのか」なんて問いを、持っている方がまだいたんだなぁって、私も嬉しかったですよ。
岩城さんがアートで救われていると思うのは、どうしてですか?
── 岩城さんが、アートに、特にパフォーミングアーツに関わることで救われていると感じる、その理由を教えてください。
岩城 3歳の頃からバレエを続けていたのですが、バレエをやれば友達ができると思っていました。中学生になるまでアメリカのニューヨークに長く住んでいたのですが、バレエは言語や国籍を超えますからね。
ブロードウェイのミュージカルや、バレエも父に連れられてよく観に行っていました。日本に戻ってきてからは歌舞伎や劇団四季とか宝塚も観るようになりましたし、東京の小劇場がたくさん集まっている下北沢で暮らしていたこともあり、パフォーミングアーツが他のひとより身近な存在だったとは思います。
── ジャーナリストとしてお仕事をされる中で、題材やテーマがパフォーミングアーツなのは、その頃の経験が影響しているんでしょうか。
岩城 そうだと思います。その後、演劇記者として働き始めてからはとても楽しかったのですが、もっと外の世界も見てみたいと思うようになったんですね。
それから仕事でイギリスやフランスなどに出張に行くようになり、取材の仕方一つで日本と全然違うということがおもしろくって。同時に、国内でも取材を重ねるうちに、日本のあらゆる演劇関係者と知り合ってしまったような気がしたんです。まぁ、錯覚なんですけど。でも日本語だけで発信し続けても、届けられるひとは限られている。日本だけではなくて、演劇を通じてもっと世界を広げたいと思い、イギリスへ渡りました。
というのも、私自身がかなり多国籍な環境で育ってきたから、海外出張へ行くたび「こういういろいろな価値観に触れられる環境の方が、肌に合っている」と自覚するようになったからです。
「私、コウモリだ」って思ったんです。
── ニューヨーク以外の国にも住んでいらっしゃったんですか。
岩城 タイや中国に短期間いたこともありますが、ほとんど東京とニューヨークです。ニューヨークのスカースデールという、ユダヤ人が多く住む地域に住んでいました。だからクリスマスよりハヌカというユダヤ教の祭日を祝うひとが多い環境で。
私が通っていた現地の小学校では、授業の一つとして教会に行く時間が組み込まれていました。その時間になると、クラスメイトが「私はクリスチャンだからプロテスタントの教会へ」「僕はユダヤ人だからシナゴグへ」というふうにバスに分かれていました。私も、聞かれたんですよ。「京子は、カトリックなの? 仏教徒なの?」って。でも、全然分からなかった。そうやって周りに聞かれて、初めて自分の立ち位置を考え始めました。
── わたしが小学生の頃には、そんなこと全然意識していませんでした……。
岩城 幼い頃から、私は部外者だという意識はつねにありましたね。中学校からは日本に戻って来たのですが、今でも覚えているのは、友達が「これ、すごく良いよね!」と盛り上がっている物に対して私は全然共感できなくて、何が良いのか考えているうちに一言も発さず休み時間が終わっていた、という経験です。その物に対する良さが解明できないと、会話のきっかけさえつかめなかったし、良さが理解できない自分は頭が悪いと思い込んでいたんですね。
── 周りが「良いね!」と言っていたら、その理由を突き止めずになんとなく「みんなが言うから良いのだろう」と流れてしまいがちな気がします。中学生くらいだと、特に。
岩城 それまでの私の人生では、誰かに合わせるということを一切やったことがなかったんですよね。大人になればうまく振る舞える場面でも、合わせようとすると自分がぎこちなくなるのを感じていました。
昔、コウモリが出てくる絵本を読んで「私、コウモリだ」って思ったんですよ。鳥類ではなくて、一応哺乳類だけれど、あんまりピンとこない。どちらにも分類できないけど、だからこそどちらにも属すことができるというか。
── わたしから見ると、うらやましいです。どちらの気持ちも理解できるんじゃないかと思いますから。
岩城 そういうひともいるかもしれませんね。私の場合は、小さい頃から、いろいろな文化を吸収しながら生きてきたから、一つの自分の価値基準をつくり上げるのに時間がかかったんです。誰かが善と判断することを、別のひとは悪だと主張するようなことが茶飯事だった。あまりにも多様な環境だったせいか、自分はどう思うかの判断ができませんでした。
でも記者時代に本当にたくさんのアーティストや舞台に関わる方々を取材する中で、私自身の価値観の幹のようなものが叩き上げられていったんです。
── 書くことを通じて、岩城さんの価値観が明確になっていったということでしょうか。
岩城 書くこともそうですし、実際にアーティストたちと面と向かって会話をすることで相対的に見えてきた部分もあります。
アーティストを取材する時は、彼らの哲学や思想が濃縮されていて、一度聞いただけでは理解が及ばないようなことが、よくあります。しかも、アーティストと一言に言っても、世界を舞台に活躍する有名なダンサーを取材することもあれば、日本の小劇場の若手作家を取材することもある。彼らは生きている世界が全然違いますが、私はその異なる世界を日替わりで理解しなければいけない。そうやって相手と向き合っていると、もどかしい思いをすることもありますが、自分を拡張していってくれる気もしたんです。
── “分からない他者を理解したい”という思いは、今なんとなく希薄になっているのではと感じることがあります。「分かるひとだけ分かればいい」という風潮が強いというか……その方が心地いいし、手っ取り早いから。わたしもついそちらに流れそうになりますが、それだといつまでも世界は閉じたままになってしまうとハッとして「理解しようと向き合い続ける」持久力を鍛えているところです。ものすごく、難しいですが。
岩城 私はそもそも、私一人だけで「自分」が成り立っているとは思っていなくて。周りのひとたちがいて、初めて自分が在ると思っているんですね。だから、もし自分の常識が通じなかったり、使う言語が違ったりしても、ベースは理解したいという気持ちが原動力になっています。他者を理解しようと試みることで、初めて自分のことも分かるようになるんです。
“意思のある巫女”として紡ぎ出す純度の高い言葉たち
── 書き手として、ご自身が誰かを救っていると感じることは、ありますか。
岩城 先ほどもお話したように、アーティストの話って「どういう意味?」と面食らうことも、ままあります。「私の芸術性を理解できない方が悪い」という姿勢を取る方も、時々いますしね。
だから取材をするときや記事を書くときは、巫女のような気持ちです。
── 巫女。
岩城 はい、媒体ですね、完全に。彼・彼女の言葉を、私が巫女として理解し、どう切り取って言葉にできるかをいつも考えます。私というフィルターを通して、芸術家の「神託」が伝わるように(笑)。
── 巫女として咀嚼したアーティストたちの言葉を文章に落とし込む上で、何を意識されますか。
岩城 どんな文章を書くときでも、なるべく純度が高く、ノイズが少ないものにしたいと思っています。今って、何をしていてもあらゆるノイズが入り込んでくるじゃないですか。会話中にはスマホの情報が入ってくるし、街中では不要な宣伝音が聞こえてくる。でも私は、そういった雑音とか外的要因から、純度の高い世界を保っていられる強さのある文章をつくりたいんですよ。
そのためには、対話するアーティストたちの作品のことはもちろん、制作環境とか生い立ちとか、あらゆる情報を知らなければいけない。そうすると、彼らだからこそ使うボキャブラリーが見えてくる。例えば「アングラ」という言葉を、下北沢の小劇場の劇作家が使うのと、他の拠点を持つ作家が使うのでは、ニュアンスが違ってくる。そういう、アーティストの持つボキャブラリーを理解して、彼らの持つ世界や表現を匂わせることのできる文章を構築したい。
それに、そういう純度の高いものに触れた時って、人間は気持ちがいいと思うんです。
── 確かに純度の高い文章は、あっという間に読めますし、まっすぐ届きますね。わたしが岩城さんのインタビューを読んで心を撃ち抜かれたのも、完全にその“純度”の高さゆえだと思います。
岩城 巫女として理解したアーティストたちの言葉を、書き手として純度の高い、強さのある文章にして届ける。そうすることで誰かが気持ちよく、スッと浄化される気分になったら、と。それが“救い”につながることがあるかもしれません。
立花がイギリス・マンチェスターで観てきた「SICK! Festival」のようす





これにて「ぼくらの学び」アート編は、一旦終了です。今後は、わたし自身がプレイヤーとして、今までの学びを生かした実践者として、「アート」と「救い」の軌跡をお届けできればと思っています。
「アートでわたしは救われるか」、そして「わたしはアートで誰かを救えるか」。一筋縄ではいかない非常に抽象的なテーマに、真摯にお答えいただいたすべての方に、お礼を申し上げます。(立花)
お話をうかがったひと
岩城 京子(いわき きょうこ)
演劇研究者、ジャーナリスト。ロンドン大学ゴールドスミス校演劇学部博士後期課程在籍。同大学非常勤講師。専門は日本近現代演劇史及び、西欧演劇理論・演劇社会学。ロンドン大学演劇パフォーマンス社会学研究所研究員。またパフォーミング・アーツ(演劇・舞踊など)を専門とするフリージャーナリストとしてAERA、新潮、朝日新聞などに執筆。近年はフリーのアート・コンサルタントとして、フェスティバル/トーキョーやウェールズ国立劇場などに協力。